
【張り子作家・アート大福さん】絵本のように可愛く不思議な世界。まったくの未経験から独学で作家活動をスタート。「私にもできる!」と思ってほしい
2024.02.20
子育て・教育
2020.07.24

この記事を書いた人
牧野 篤

東京大学大学院・教育学研究科 教授。1960年、愛知県生まれ。08年から現職。中国近代教育思想などの専門に加え、日本のまちづくりや過疎化問題にも取り組む。著書に「生きることとしての学び」「シニア世代の学びと社会」などがある。やる気スイッチグループ「志望校合格のための三日坊主ダイアリー 3days diary」の監修にも携わっている。
コロナウイルス禍は、これから私たちの生活にじわじわと大きな変化をもたらしそうな予感がします。いえ、本当は、私たち自身がもっと早くにその変化をつくりだしていなければならなかったのかも知れません。
「もう、後戻りできそうにない。」私の知りあいの企業家たちは、異口同音にこういいます。そして、こう続けるのです。「そうなのだろうと気づいていたのに、なかなかそうできなかった。それが、コロナ禍でどうしようもなくて、切り換えてみたら、やはりそうだった。もっと早くにそうしていたら、いまごろもっと違う風景を見ていたに違いない。」
緊急事態宣言が出され、外出自粛が要請されたとき、私の大学がオンラインでの業務に切り換えたように、多くの企業が、どうしても必要な現業部門を除いて、多くの業務をオンラインに切り換えて、在宅勤務を奨励しました。ほぼ一斉に、といってもよいほど、一斉に切り換えられ、私の知人の大手通信事業者の幹部などは、回線が逼迫してしまって、監視要員を増やしたといっていたほどでした。
このことに見られるように、わたしたちの社会にはすでにオンラインで仕事をし、オンラインで交流することができるハードウエアの条件は整っていたのです。しかし、それをしようとはしてこなかった。そう、知人の企業家たちは悔いているのです。

なぜなのかといえば、何となく、としか理由は見当たりません。切り換えなくても、これまで通りにやっていれば、問題なく仕事はできていたし、とくに切り換える必要も感じないでいられた。だから何となく問題ないし、それでいけるような気がしていた。そして、切り換えることも何となく面倒だし、何となく難しいのではないか、と感じていた。
オンラインだと、直接会って話をするよりも、顔の表情や息づかいなど言葉以外の情報を得ることが難しくて、うまく仕事が進まないのではないかと、何となく思っていた。だから、あまりよくないのかな、と思っていたし、切り換えなければ困るわけでもないし、何となくそのまま来てしまった。こういうことなのです。 それはまた、この社会がそれだけ余裕があったということかも知れません。しかし、今回コロナ禍でやむなく切り換えてみたら、もう、後戻りできない、というのです。もう、おわかりではないでしょうか。

オンラインのソフトが充実していて、リモートワークでもほとんど支障なく仕事ができることが分かってしまったのです。しかも、これは会社だけでなく、従業員にとってもとてもメリットがあることも分かってしまった。
会社は、これまで何となく年間数千万円というような出張旅費を組んで、支出してきたが、これが要らなくなることが分かってしまった。しかも、移動時間を他の仕事に当てることもできて生産性が上がることが分かってしまった。もう、空間的な距離は問題ではなくなり、その結果、時間を節約することができ、それが経費の節約になって、さらに生産性の向上につながっていく。
単に会社の経費だけを考えても、こんなにメリットがあることが分かってしまった。しかも、これまででしたら、オンラインでは失礼ではないかと考えていた相手とのやりとりも、お互いにコロナ禍で自粛要請が出ているから仕方がないね、といってやり始めてみると、相手も結構いいじゃないかということになり、オンラインで十分に仕事が進められることが分かってしまった。こういうのです。
その上、従業員にとっても、いいことがたくさんあったといいます。毎日、あの満員電車に寿司詰めにされる「痛勤」をしなくても済み、朝もゆっくり起きて、ゆっくり食事をとり、余裕を持って、仕事ができることが分かってしまった。飲み会ができないことがちょっと寂しいけれど、オンライン飲み会をやってみると結構楽しいし、家族持ちは家族との時間をたくさん持つことができて、幸福感が上がった。こういうことが分かってしまった。

もちろん、日頃あまり長い時間一緒にいなかった家族が仕方なく一緒にいることで生まれる軋轢があり、また仕事に子どもが乱入したり、家族との間で感情の行き違いがあったりすることもあったけれど、総じて見れば、いいことがたくさんあることが分かってしまった。こういうのです。
その上、こういうことが分かってくると、あの満員電車こそ、仕方なく乗っていたけれど、自分が望んで乗っていたのか、いや、そうではない、つらかった。駅ビルがどんどん開発されて、駅に商業施設が集積して、自分もそこに出かけて、人混みの中で買い物をしていたけれど、それは自分が望んだことだったのか、いや、そうではない。確かに新しいモノがどんどん溢れてきて、楽しくはあったけれど、無理して行かなければならない場所でもなかったけれど、そうした方がいいような気がして、そうさせられていたのではないか。
こういう思いがどんどん出てきて、自分たちには何でもある、何でも選べるというある種の万能感を持っていたけれど、結局は、そうさせられていたのではないかという疑問が生まれて、自分の生活を見直すことにつながったといいます。 なんだか私のひきこもり生活と同じです。
しかも、これも知り合いの不動産業者の話ですと、オンラインで仕事ができることがわかってくると、都心にこんなに大きなオフィスは要らない、という企業が続出して、オフィスを縮小したり、解約したり、都心から郊外の住宅地で通勤環境も自然環境もよくて安価な空き家に拠点を移したいという企業からの問い合わせがひっきりなしにあるというのです。
多くの企業がオンラインでの勤務を始めることで、仕事の仕方が変わり、生産性が高まる経験をし始めているのと同様に、不動産業者ももう空間を開発して、貸し出してお金を儲けるという時代は終わりつつある、というのがその知人の話なのです。
これまでは、企業の収益が、人が移動し、集中することを基本に考えられていて、より効率的に、という考えの中で、都心に一極集中すれば、その方が生産性も上がると考えていた。だから、都心に空間を開発する、つまり狭い土地に集積するかのようにして高層ビルを建てて、それを売ったり貸したりすることが収益につながっていた。しかしこれからは、そういう空間をつくり、切り売りすることで金を儲けるモデルが終わりを告げるのではないかというのです。

確かに、このコロナウイルス禍のもとで、私のところに持ちかけられるまちづくりの相談にも変化が見られます。たとえば、地方の駅前再開発の相談などでは、これまではいくら口を酸っぱくして、どこにでもあるような駅前のデザインにしてしまっては絶対に人が来なくなるし、駅前の商店街も、歴史的につくられてきたモノを大切にしないで、どこにでもあるアーケードのようなものにしてしまっては、人を惹きつける力がなくなるといっても、なんだか再開発して地価さえ上がればそれでいい、というような相談が多かったのですが、そういうものではもうダメではないかという相談に変わってきています。
ようやく、という感じではあるのですが、空間やハコモノではダメだということが社会の雰囲気として伝わり始めたということかも知れません。
実は、社会の変化に敏感で、オンラインでの仕事に対応できていたIT企業などでは、早くから一部の子育て世代の社員の仕事をオンラインに切り換えて、たとえば週一、月一勤務などにして、家族で自然環境がよくて、子育ての条件が整っているいわゆる地方都市に滞在させ、自社の仕事をすることとともに、地元の役場の仕事や町内会などの仕事を請け負うことを奨励していた企業があったのです。
またその企業では、長時間働けない障害者にも、給与を正規社員と同じ時間給になるように調整して、短時間での勤務を保証していました。誇りを持って働けるようになると、障害を持った人たちもできる仕事はいくらでもあるといいます

この会社の役員に聞きますと、オンラインで仕事ができて、きちんと給与を保障されれば、距離や時間は問題ではなくなるし、大都市にいる意味がなくなる。子育て世代が重視するのは、子どもが走り回れる環境と、公立学校できちんと教育を受けられること、さらにかかりつけ医を持つことができること、そして地元に受け入れてもらえて、自分も地元に役立つこと、もっといえば地元におもしろい文化が伝わっていること、そういうことになるのではないか、ということです。
そして、確かに、地方に住まわせた社員の生活満足度は高く、生活が楽しくなったり、地元での自分の役割に誇りを持ったりすることで、仕事でも生産性が上がったといいます。すでにアメリカでは企業主導で、そして欧州では法的に、従業員の在宅勤務の権利を保障しようという動きが出始めています。
こういう地殻変動が起こっているのです。ですから、私の知人の企業家たちは、こういうことを知ってしまった以上、もう後戻りできないというのです。
もともと理想的なネット社会というのは、こういうことが構想されていたのです。人がオンラインで繋がりあうので、移動することが減り、移動時間が節約できる。その分、家や地域コミュニティで過ごすことが増え、それが地域の人間関係や趣味などの交流を豊かにして、余裕を持った生活ができるようになる。そうすることで、会社につながれた生活ではなくて、自分で生活全体をコーディネートできるようになる。こういわれていました。工夫の仕方によっては、このような生活ができる条件が整ってきたということでしょう。
しかしその反面で、どうも変わらないなあ、と思ってしまうのが学校と行政機関です。緊急事態宣言が解除となった途端に、行政の審議会が動きはじめ、対面での会議を行うとの連絡が続いています。さすがに文科省の審議会は、オンラインで行うとの通知が来ましたが、今できるのなら、この4ヶ月間の空白は一体何だったのかと、改めて疑問がわきます。ハードの整備ができていなかったということよりは、オンラインで審議会をやることの是非をめぐって、意思決定できなかったということなのではないでしょうか。

対面での会議を行うという通知に対して、オンラインで行えないのかと問い合わせると、決まってセキュリティの関係でオンライン会議は禁じられているという回答が来ます。確かに脆弱性が指摘された会議システムもありましたが、民間企業が使っているものはどんどん改良されていて、セキュリティも脆弱性がなくなってきています。そもそもそんなこといいだしたら、日頃から使っているワープロや表計算などの統合ソフトウエアの脆弱性は問題ないのか、と突っ込みたくなります。
そして、学校です。新学期からオンライン授業を展開している私学と、それができないで、登校日をつくって分散登校させては、宿題を出して、それを持ってこさせている公立学校とでは、すでに学力差がついているのではないかといわれたりしています。前回のコラムに書いた、私が6月1日の朝、出会った中学生がいみじくもいっていたように、「オンラインの授業は授業ではない」と考えている先生方も多いのではないでしょうか。でも、彼がいっていたように、オンラインで様々に開講されている教科の授業の方がおもしろい、という子もいます。
このような学校や行政のとても硬い態度に、企業が何となく惰性でやってきてしまって変われなかったということ以上の何かを感じとってしまうのは、私だけでしょうか。私はそこにある種の頑なさとでもいうべき信念のようなもの、つまり学校とはこうあるべきで、行政とはこうあるべきであって、それを守り通すことが善いことなのだとでもいうような、頑固さのようなものを感じてしまうのです。
そしてその頑固さは、自分が変わることを拒むこと、そのさらに裏には変わることへの恐れのようなものがあることに自分で気づいていて、そういうことを打ち消して、合理化するための論理(私の父の世代の人たちにいわせれば、屁理屈)を潜ませたものであるように感じられてなりません。

変わりたくないから、変わらない方がよいといっている、こう受け止められるのです。その背後には、財政的な問題から、ICT環境の整備が公的な機関であるほど遅れているという事態があることも承知しています。私が専門としている社会教育や生涯学習の施設とくに公民館などは、その極北にあるといってもよいでしょう。
しかしこういう頑なな変わらなさの背景には、学校も行政もどちらもが、保護者や住民からのクレーム対応に教員や職員が疲れ切って、内向きになってしまっていること、そういうことがあるのではないでしょうか。変わることへの恐れとは、そこから生まれているのではないでしょうか。学校や行政は、ともに子どもを育て、ともにこの社会をつくり、よりよい社会を次の世代に受け渡していくという使命感や誇りを持つことができなくなってしまっているのではないでしょうか。
そして、学校や行政がこのような頑なさを持ってしまわざるを得ないのは、保護者や住民たちそのものが、お互いにクレームをつけあって、不信感に囚われてしまうような状況におかれているからなのではないでしょうか。ともにこの社会に位置づいて、ともにこの社会をつくっていると思えず、自分でもどうしたらいいのか分からなくて、イライラしている人々の、恰好のイライラのはけ口が、学校や行政なのではないでしょうか。
私たちはよく、当事者として、他人の身になって、といいます。そして、それは社会生活を送る上で、大事なことに違いありません。しかし、この当事者として受け止める、という当事者性のあり方や、他人の身になってというときの他人の身になるなり方とは、一体どういうことなのでしょうか。
たとえば、ネット空間における不利益(被差別や被害)に関する議論を取り上げてみます。従来、一般的には、当事者といえば、加害者と被害者の双方であり、それをとりまく人々は部外者でした。そこでは、他人の身になるという場合、自分を被害者に置き換えてみて、また加害者に置き換えてみても、その痛みをそのまま感じることができない、だからこそ、一旦立ち止まって、想像力を働かせて、共感して、その痛みが広がらないように、同じような経験をする他人が増えないように、と心を配り、不利益を被る人を減らそうとする、そういう心の動きや行動があったはずです。それを当事者性といいました。

しかし、昨今の当事者性というのは、不利益を被る人がいると、多くの人が自分はその被害者と同じ立場にあるとして、自分自身が傷つけられたかのような反応を示し、それが躊躇のない「正義」の根拠として立ち上がり、その「正義」に依拠した反論や批判が、それこそ炎上するかのようにして、加害者へと向けられる、こういうことが起こってはいないでしょうか。
そこでは、社会がわれわれとそうではない人々との二つに切断されてしまいます。白か黒か、味方か敵か、こういう明確な線引きがなされ、お前はどちらなのかと立場表明を迫られるのに、その線引きの基準は曖昧で、その時々の関係のありかたによって揺れ動いている。そして、敵・味方で「正義」の応酬が繰り広げられる。こういうことになってはいないでしょうか。
被害者に寄り添うのではなく、加害者によって自分の尊厳が傷つけられたかのようにして、本来の当事者以外の人々から、まっすぐに、曇りなく、躊躇なく、「正義」の反論や批判が、加害者とされた人に向けられるのです。そこには、自分の感じ方がもしかしたら世間の感じ方とはズレているかも知れない、もしかしたら却って人を傷つけることになるかも知れないという、立ち止まって、自分を一旦相対化してみる、そういう心の揺れのようなものは存在していません。そこで主張されるのは、自分の尊厳や気持ちが傷つけられ、気分が悪いというような、どこまでいっても自分しか存在しない当事者性なのではないでしょうか。
「みんなちがってみんないい」といいます。確かにその通りです。でもその違っていることを「いい」と判断しているのは誰なのでしょうか。それは「みんな」なのではないでしょうか。そしてその「みんな」とは自分がいる側の人たち、ということになってはいないでしょうか。それはそのまま長いものに巻かれろ、という話につながってしまいます。
これが面倒なのは、「みんな」が「いい」といっていることに自分を合わせなければならないという論理が滑り込んでいること、つまり集団の同調圧力がかかっているということです。このように見ていくと、先ほど述べた当事者性とこの「みんなちがってみんないい」という論理とは相似形であることがよくわかります。

企業の雇用構造が変化し、家族の形も変わり、子どもの貧困が顕在化し、また地域社会が解体の度合いを深めることで、この社会では人々の孤立が問題となっています。孤立する人々は、寄る辺を失い、自分の尊厳を保ち、また生活を維持する術がわからず、どうしたらよいのか不安ばかりを貯め込んでいくのではないでしょうか。そして、自分ばかりが損をしている、正直に生きている自分はバカを見ている、社会には不正をして利益を得ている人がいるに違いないと思い込んでいくのではないでしょうか。
そして、人々は、他者を思いやり、想像するのではなく、自分は被害者だとして、そして自分こそが「正義」だとして、加害者と見なされた他者や不当に利益を得ていると見なされた他者、つまり「不正義」を匿名で糾弾する、こういうことになってはいないでしょうか。それはまた、本来の当事者性というものではなく、差別と孤立という事態によってつくられた無数の当事者という、いわば架空の存在、つまり「みんな」なのではないでしょうか。誰もが当事者になり、自己主張するようになるのです。
しかし、この当事者性は、ここでは他者との関係における、他者への想像力に支えられた、慮りによって成立するのではなく、それはそのまま自分だけ、つまり当事者としての自己を無数に立ち上げることになってはいないでしょうか。そこでは、誰もが皆当事者なのであり、気づいてみたら、本当の当事者の姿が見えなくなってしまっていたということになってはいないでしょうか。

その上、この当事者のあり方は、そのまま一人ひとりが孤立して、その孤立を自己責任だと見なす論理へと転じてしまいます。しかも、この当事者である自己は、自分を当事者だと認めろと他者に主張するのみで、当事者であることの権利保障の請求先を失って、一層孤立してしまいます。
なぜなら、誰もが自分を当事者だと認めろと他者に要求するばかりで、そこにあるのは自己主張のいがみあいだけだからです。そして、行政的な支援も求めることができなくなってしまいます。なぜなら、自分だって自分でなんとかしようとしているのに、行政に支援を求めるなんて甘えているし、「不正義」だからです。こうして、行政的な支援を求めることに対しても、人々がお互いに牽制しあうことになってしまいます。これが自己責任社会の構図なのではないでしょうか。
また現実には、この主張する自分は権力や権威さらには多数者への依存を招く、つまり長いものに巻かれろという心性を生み出してしまいます。なぜなら、自分の側にあるのがそういう強い集団であるべきだからです。こうして、政治は容易にポピュリズムと化し、人々は政治によって癒やされることで、権力との同一化を図り、自分とは異なる人々を攻撃するようになります。「正義」を手にするのだといってよいでしょう。
この構造は、当事者を個性と読み換えても変わらないのではないでしょうか。誰もが他者に対して自分の個性を認めろと主張しあうことで孤立して、いがみあっているのが、現実の「みんなちがってみんないい」社会なのではないでしょうか。
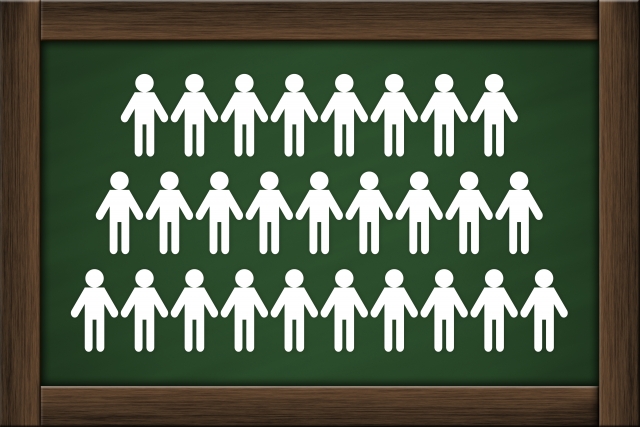
誰もが被害者だと言い募る。誰ともかかわりを持たず、誰にも寄り添わず、誰のことも想像することなく、砂粒化した人々が、自分こそは被害者だと言い募り、加害者を躊躇なく糾弾して、炎上する。しかもその加害-被害関係は、常に流動する。
こういう関係ともいえない関係に人々は置かれていて、自分も被害者であり、当事者なのだと、その位置を探ることに汲々としているのではないでしょうか。だから人々はあらゆることの傍観者になってしまいます。自分も弱い存在なのだから、自分のことが認められなければならないし、自分こそが守られなければならないのだけれど、それは自己責任の結果であるべきだ、だから「みんな」と同じにしていなければならない、そうでなければ糾弾されてしまう、こういう感覚が社会を支配しているのではないでしょうか。これを武田砂鉄さんは「空気」ではなく「気配」といいます。
日本の気配(武田砂鉄著)
私たちはこの「気配」に支配されて、自分こそは当事者だと訴えつつ、あらゆることに対して傍観者となってしまうのではないでしょうか。「みんな」の側にあることで。そして人々は常に自分は「みんな」の側にあるのかどうか、「みんな」からの「評価」に晒されていると感じ続けてはいないでしょうか。
どこに行っても「正義」を我が事とした「みんな」によって、評価がついて回り、自分は「みんな」に晒され続ける。こういう感覚が、人々の間で共有されてしまってはいないでしょうか。そして、自分も実は、その「正義」によって、この社会をつくり、不正義を糾弾する側にいるけれど、それは、本当の当事者とは異なるところで、当事者がつくられて、自分のことだけを言い募ることになってしまっている。
つまり、自分こそが弱い当事者なのであり、守られなければならない唯一の存在なのだ。だから、他人などに構ってはいられない。それどころか、他人のことなどわかろうはずがない。自分だけを守らなければならず、自分だけが大事なのだから。こういうことになってはいないでしょうか。
けれども、自分を守ってくれと請求する先を、この当事者は予め失っています。なぜなら、すべての人々が皆そういう弱い当事者として、他者に自分を認めろ、守れと主張しているからです。そして、自分と同じような価値や心性を共有しているマジョリティに同調して、自分こそは当事者だと主張する多数の傍観者が生まれることになります。
しかも、この当事者は、「正義」によっていかようにも反転しつつ、人々に本当の当事者に寄り添うことをできなくさせてしまいます。いつ何かの拍子に、今度は自分がその「正義」によって糾弾されかねないという不安を抱えているのではないでしょうか。声を上げたら危ない、と。なぜなら、当事者だからです。当事者は孤立しているのです。
そしてその不安やイライラのはけ口が学校や行政だということだとしたら、私たちはどうしたらよいのでしょうか。

この社会の変われなさの原因は、「みんなちがってみんないい」といいつつ、「みんな」がお互いに牽制しあっている、そういう「気配」に支配されてしまっているからなのではないでしょうか。
こんなことをブツブツつぶやいていたら、オンラインの会議をやっていた子ども居場所づくりのおばちゃんに一喝されてしまいました。
「先生、なにブツブツいってるの! みんなちがってるのって、当たり前じゃない!」
そうか、あったり前じゃん!
「みんなちがってみんないい」なんていっているから、「みんな」が気になって仕方がないのでしょう。それを突き抜けるのは「みんなだろうが誰だろうが関係ないよね、だってみんなちがってるんだから」という当たり前の論理なのです。
であれば、学校や行政が「みんな」の不満や鬱憤のはけ口になるのではなく、この社会を次の社会へと新たにつくりだしていく役割を担い、誇らしい場所になるためには、防衛的になっているのではなくて、この社会を突き抜けて、最先端へと反転すること、そういうことなのではないかと思います。
では、その反転攻勢の方途はあるのか。これが次の課題となりそうです。
\ 人生100年時代の社会のグランドデザインを描く/
\ 最新情報が届きます! /
牧野先生の記事を、もっと読む
連載:子どもの未来のコンパス
#1 Withコロナがもたらす新しい自由
#2 東日本大震災から学ぶwithコロナの中の自由
#3 Withコロナで迫り出すこの社会の基盤
#4 Withコロナがあぶりだす「みんな」の「気配」
#5 Withコロナが呼び戻す学校動揺の記憶
#6 Withコロナが再び示す「社会の未来」としての学校
#7 Withコロナが暴く学校の慣性力
#8 Withコロナが問う慣性力の構造
#9 Withコロナが暴く社会の底抜け
#10 Withコロナが気づかせる「平成」の不作為
#11 Withコロナが気づかせる生活の激変と氷河期の悪夢
#12 Withコロナが予感させる不穏な未来
#13 Withコロナで気づかされる「ことば」と人の関係
#14 Withコロナで改めて気づく「ことば」と「からだ」の大切さ
#15 Withコロナが問いかける対面授業って何?
#16 Withコロナが仕向ける新しい取り組み
#17 Withコロナが問いかける人をおもんぱかる力の大切さ
#18 Withコロナで垣間見える「お客様」扱いの正体
#19 Withコロナで考えさせられる「諦め」の怖さ
#20 Withコロナ下でのオリパラ開催が突きつけるもの
#21 Withコロナで露呈した「自己」の重みの耐えがたさ
#22 Withコロナであからさまとなった学校の失敗
#23 Withコロナの下で見えてきたかすかな光・1
#24 Withコロナの下で見えてきたかすかな光・1.5
#25 Withコロナの下で見えてきたかすかな光・2
連載:学びを通してだれもが主役になる社会へ
#1 あらゆる人が社会をつくる担い手となり得る
#2 子どもたちは“将来のおとな”から“現在の主役”に変わっていく
#3 子どもの教育をめぐる動き
#4 子どもたちに行政的な措置をとるほど、社会の底に空いてしまう“穴”
#5 子どもたちを見失わないために、社会が「せねばならない」二つのこと
#6 「学び」を通して主役になる
新着コンテンツ