
【張り子作家・アート大福さん】絵本のように可愛く不思議な世界。まったくの未経験から独学で作家活動をスタート。「私にもできる!」と思ってほしい
2024.02.20
子育て・教育
2022.02.25

この記事を書いた人
牧野 篤

東京大学大学院・教育学研究科 教授。1960年、愛知県生まれ。08年から現職。中国近代教育思想などの専門に加え、日本のまちづくりや過疎化問題にも取り組む。著書に「生きることとしての学び」「シニア世代の学びと社会」などがある。やる気スイッチグループ「志望校合格のための三日坊主ダイアリー 3days diary」の監修にも携わっている。
コロナ禍の中で2回目の新年を迎えました。
思い返せば、国内で新型コロナウイルス感染症の感染が確認されたのが、ちょうど2年前の1月でした。その時には、ここまで大きな社会問題となるなどと誰もが考えたこともなかったのではないでしょうか。
それから2年、私たちは新しい生活様式をつくり、それに慣れることを強いられ続けてきました。当初は、様々に戸惑いがありましたが、次第にそれが日常生活の中に溶け込み、人々はそれぞれに新しい生活を楽しもうとする動きを探し始めているように見えます。

反面で、経済活動は大きく制約を受け、コロナ禍以前から社会に深く進行していた貧困や孤立などの問題が、一挙に目に見えるようになったのも事実です。私たちは、これらの現実から目をそらすことなく、これからの社会の在り方を考えなければならなくなっています。
そのうえ、気候変動など国境を越えた全地球的な問題もわたしたちの社会を直撃しています。
いまや私たちは、身の回りのちいさな出来事から全地球的な課題までを、日常生活の現場で引き受け、それでも生き抜いていくことを求められる時代に立ち至っています。
コロナ禍での新しい教育の在り方を考えようとしたこの連載もこんなに続くなどとは、連載開始当初は考えてもいませんでした。
そして、これは私の癖なのか、いえ、そうはいっても研究者としてはそうせざるを得ないというのか、様々な問題をとらえることで、それをどう考えたらよいのか、どう解決できるのか、どう次の一歩を踏み出せばよいのか、そういうことを考えるのが私たちの仕事なのだと思えば、この連載が悲観的な論調を持ったものであったことは、否めないのではないかと思います。
この連載を読んでくれていた知人が、お前の議論はどうも悲観的になっていかん、といっていましたが、そのとおりだと思います。
コロナ禍でこの社会が抱えていた様々な矛盾や問題が、あからさまになったという面は否定しがたくあるのではないでしょうか。子どもの貧困は言うに及ばず、私たちが日々の生活に追われて、気づきもしなかったことが、ふと社会の表面に浮き上がってきて、心を乱される、そういう経験をこの2年間否応なくさせられてきたのではないでしょうか。
そして、気がつけば、日々の生活に追われて、社会のことが見えなくなっていた、そのことそのものが、自分の生活を貧しいものにしてしまっていた、そういうことにハッとさせられることも増えたのではないでしょうか。
緊急事態宣言が解除となり、飲食店が通常の営業に戻っても、夜の8時や9時には飲み屋街から人が減り、皆、帰宅を急ぐようになったとの報道がありました。
単に感染防止に心がけているということだけではなくて、緊急事態宣言下で、テイクアウトに慣れ、自宅で家族と過ごす時間の大切さや愉しさを覚え、地域コミュニティで隣人たちと触れあうことで、会社の同僚とは異なる人々がこんなにもいることに目を開かれ、何気ない世間話の多様性に驚いたという知人も少なくありません。

リモートワークで仕事ができることを発見し、以前は、嫌な思いをしながらも、当然だと思っていた長時間の「痛勤」ラッシュやだらだらと続けていた長時間労働、そうしたことが「やはり」おかしかったのだと改めて気づいたという知人・友人は、東京を離れてしまったベンチャー系の知人だけではなく、ごく普通のサラリーマンであった人たちの中にも少なくありません。
皆、新しい生活を「発見」したのです。
その反面で、子どもたちも含めて、人と直接会えないことの寂しさやつまらなさを改めて感じたという人もたくさんいます。直接対面して、触れあい、体温を感じとること、それは単に肌を触れあうことだけに限りません。ことばの温度を感じとること、その大切さを改めて感じた人も大勢いるのではないでしょうか。
さらにその反面で、これまで「対面のもつ暴力性」に晒されて、人と会うことができなかった人々は、オンラインという新たなつながり方が広がることで、人と出会い、語りあうことの愉しさを覚えたのではないでしょうか。私の学生にもいる引きこもりがちの若者たちも、「二次元平面なら大丈夫です」といいつつ、オンラインのセミナーなどにどんどん参加してくれるようになったのが、印象的でした。

これらコロナ禍での日常生活の一部を振り返るだけでも、そこでは、人が人と出会い、つながりあうとは一体どういうことなのか、私たちという存在は本来どういうものなのか、という深い問いが、それぞれの生活の場において発せられていることを感じ取れるのではないでしょうか。
私たちは、気づかないうちに、何気なくおかしいと思いつつ、そのままにしてきてしまっていた、日常生活の中のちいさな棘に気づき、それを抜こうとし始めているように思えます。
そして、自己弁護的にいえば、この連載はこの棘の輪郭を明らかにするだけでなく、その在処や来歴を探ろうとしたのだといえます。そうすることで、私たちはそのチクチクと心乱す棘を具体的な質感をもってとらえ、それを抜く時の痛みに耐え、傷を癒やし、次の一歩を踏み出そうとする勇気と羅針盤を持つことができる、そう思います。
コロナ禍は不幸なことでしたし、それはいまも続いています。しかし、私たちの先達が社会の危機のたびに、新たな社会の在り方や制度を生み出して、それを次の世代に伝えてきたように、私たちにもこの2年間の苦しい経験の中で、少しずつ新たな社会のありようについてのかすかな光が見えてきているのではないでしょうか。
今回からは、このかすかな光をとらえて、希望の持てる社会へと歩むためのコンパスを探ろうと思います。
コロナ禍の渦中に、各地の自治体で新たな教育振興基本計画の策定が進められました。私もいくつかの自治体の策定審議会の委員でした。
その中で、東京都杉並区の教育振興基本計画(新教育ビジョン)の策定は、とてもスリリングでした。学校支援地域本部の設置など、国の学校教育行政にも大きな影響を与えるような、先駆的な取り組みを進めてきた杉並区ですが、私が座長を務めた新教育ビジョン策定審議会で、ある試みを行ったのです。
事前に事務局ともあまり十分にすりあわせをしないまま、私が初回の会合で「座長権限」で昨今の社会状況や国の教育政策の動向などのブリーフィングを行い、これからの学校教育を考える上で大切なことを委員の皆さんにお伝えしました。その上で、私から「座長の独断ですが」と断った上で、「これまでのような10年計画をつくるような教育ビジョンはやめにしませんか」と提案したのです。
つまり、10年後の子どもたちのあるべき姿を描き、それにもとづいて区の教育とくに学校のあるべき姿を描いて、その姿を表示する数値目標を定め、そこからバック・キャストつまり逆回しにして、今年は何をする、来年は何をする、と決めて、その都度、評価を繰り返して、次年度の目標数値を設定する、というような数値達成型の計画はやめにすること、10年後の社会がどうなっているのか、私たち自身にはわからないのだから、そして人生を歩むのは子どもたち自身なのだから、子どものあるべき姿をいまのおとなたちが決めるのではなく、子どもの教育にとってどうしても譲れない価値をおいて、それを基本として、どういうかかわりを子どもたちにしていくことができるのか、そして子どもたち自身が学びをどう進めていくのか、そういうことを考えませんか、と委員の皆さんに問い掛けたのです

委員の皆さんは、小中学校の校長先生、区の教育にかかわる様々な団体の代表者、福祉関係者、そして公募区民、さらに私たちのような学識経験者と呼ばれる人々で構成されていました。
私からの問い掛けに、はじめはどなたもが戸惑いの表情を浮かべました。教育委員会の事務局担当者も、えっ、という顔をしています。いったい、座長は何をいいだしたのか、と。私も皆さんの表情を見て、ちょっとフライングだったかな、事前に話のすりあわせをしておくべきだったか、と少々反省しはじめたその時でした。
「そのお考え、素晴らしいと思います。」
「10年後の目標数値をいま決めても、実現できるとはとても思えません。それは達成できないということではなくて、いま決めた目標が実現できるような社会ではなくなっているのだろうということです。」
「私たちも、10年後の目標を決めて、それを達成するための施策を考えるなんて、何かおかしいと思っていたのです。」
「未来に生きるのは子どもたちです。もう、いまのおとなが子どもたちの人生を決めてしまうようなことはやめにしましょう。」
「座長のご提案、大賛成です。」
との声が、全委員から上がり、全会一致で、新教育ビジョンでは、目標や数値を決めないことがあっさりと決まったのです。
しかし、教育ビジョンです。では、何を検討するのか。このことで議論が百出しました。そして、結果的に決まったのが、これからの社会を生き抜く子どもたちには、人生100年を生きるための基礎を養うこと、そのためには人としてどうしても譲ってはならない「価値」があること、こうしたことを基本として、区の教育行政の在り方の方向性を考えること、このことが決められたのです。

譲れない価値とは何でしょうか。それは、何よりも「命」です。その次に大切なのは一人ひとりが共に認めあい、尊重しあう「尊厳」、そしてこの社会で生きていくために保障されなければならない「人権」がある。こういう話になりました。
新しい教育ビジョンは、「命」「尊厳」「人権」を譲れない価値とおき、その上で何を目指すのか。「命」「尊厳」「人権」は、子どもたちだけでなく、おとなである私たちにとっても、私たちが社会に生きていくためになくてはならないものです。でもそれは、目指すべき方向性ではありません。それらを大切にすることは、どうしても譲ることのできない最低限の条件です。
では、何を教育が目指すのか。その方向が検討されなければなりません。こちらも議論百出でした。そして、最後に委員の皆さんがそれぞれの思いを心に抱きながらも、同意した、杉並区の教育の基本的方針が「みんなのしあわせをつくる教育」でした。
しあわせのあり方は、人それぞれ異なります。このことを認めることが、先ずは大切です。それは「命」「尊厳」「人権」を大切な価値とすることからも当然導かれる観点です。しかし、自分のしあわせを求めることで、人のしあわせを壊してしまってはなりません。
しあわせを求めることは、自分のしあわせだけでなくて、いえ、むしろ自分のしあわせを求めるのであれば、他人のしあわせをも大切にしなければなりません。
譲れない価値をおくと、一人ひとりが生きることそのものが、身勝手な、独りよがりなことではなくなり、見ず知らずの人たちのしあわせをも我が事として引き受けること、こういうことにつながっていきます。

ですから、「しあわせをつくる教育」ではなくて、「みんなのしあわせをつくる教育」なのです
こう考えてくると、教育ビジョンの作り方も変えなければなりません。
これまでは、策定審議会に集まった委員、当然おとなたちです、がそれぞれの立場から意見をいい、それぞれの立場から子どもたちの将来を考えて、あるべき姿を描き、それを実現するための目標を議論してきました。しかし、3つの大切な価値をおき、「みんなのしあわせをつくる」ためには、おとなだけで議論することは許されません。
また、多くの区民の声を聞かないで、策定審議会だけで議論することも避けなければなりません。
そこで、今回の教育ビジョンの策定では、これまでは、策定されたビジョンを区民にお披露目する場であった区民教育シンポジウムを策定過程のはじめの方で開催して、新しい教育ビジョン策定の考え方を伝えると共に、参加した区民の間でワークショップをおこなって、一人ひとりの区民が考えるこれからの教育について議論してもらうことにしました。
さらに子どもたちに、学校はどういうところなのか、どんな学校になって欲しいのか、杉並区の好きなところとこうした方がいいと思うところ、そしてどんな言葉をかけられたら一番うれしいか、などをすべての学校を通しておこなったアンケート調査で聞くことにしました。
その結果、次のようなことがわかったのです。これまで杉並区の教育は「共に学び共に支え共に創る教育」を教育行政の柱にしてきました。この取り組みを通して、子どもたちは着実に「共に」学び、支えあい、そして教育をつくる主役へと成長している、このことがわかったのです。
子どもたちの回答を見てみると、小学校低学年の子どもたちは、学校のあり方を自分と友だち、自分と先生という関係で受け止め、それが高学年になると、その関係を基礎として、学校の施設のあり方や使い方に思いが開かれ、中学生になると自治という観点が生まれてきて、みんなが気持ちを通わせ合い、みんなが仲間を自分事のように考え、みんなが主役になる学校を求めていることが見えてきました。
それは、シンポジウムでおとなたちが杉並区のよいところを生活しやすい、緑が豊か、生活環境がよい、子どもたちには自分で自分の人生を切り拓く力をつけて欲しい、と願っていることに対して、子どもたちはみんなの仲がよい、おとなが子どもを大切にしてくれる、おとながよい環境を整えてくれている、とより人間関係に着目した見方を示していることにも表れていました。
そして、いわれてうれしい言葉は?と聞いた問いで、回答が最も多かったもの(自由記述)は「ありがとう」だったのです。「ありがとう」といってもらうためには、まず自分から相手に何かしなければなりません。しかもそれが相手の感謝に繋がるためには、相手のことを慮り、相手のことを自分事にして、手を差し伸べなければなりません。
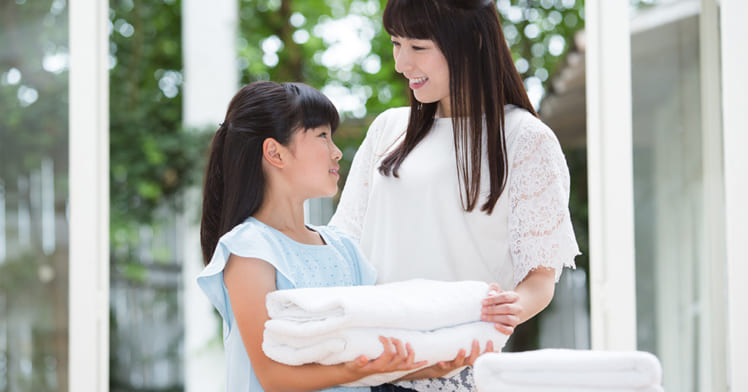
こういう子どもたちが確実に育っている。このことは、策定委員の皆さんの心に深く刻まれました。
そしてもう一つ、大切なことに気づかされました。確かな子ども観を私たちおとなが持つことの必要性です。人生100年をいきいきと生き、自分のしあわせをみんなのしあわせと重ねて考え、社会を担う主役として育つためには、多様性と共生を自分のものにする必要があります。それはまた、ちがいを認めあうこと、ちがいを受け入れあうこととして子どもたちのあり方に反映します。
そして、「ちがい」を「ちがい」として認め、尊重し、受け入れあうことの基礎には、自分が他人や自然・社会つまり自分の周りの環境を、不思議だと思い、驚き、触れてみようとし、それを大事にしようとする感性が必要です。それは、アメリカの海洋生物学者レイチェル・カーソンが訴えていた「センス・オブ・ワンダー」でもあります。
カーソンは、いまからもう半世紀以上も前、名著『沈黙の春』(レイチェル・カーソン、 青樹簗一訳『沈黙の春』新潮文庫など)を著して、農薬など化学物質の環境破壊に警鐘を鳴らしたのですが、この彼女が大切だと訴えたのが、子どもたちの持つ「びっくりする力」「不思議に思う感性」つまりセンス・オブ・ワンダーでした。
▶レイチェル・カーソン、 青樹簗一訳『沈黙の春』(新潮文庫)
しかも、彼女は、子どもたちのセンス・オブ・ワンダーが発揮されて、彼らが好奇心に誘われて、環境の不思議を探求することができるためには、安心して驚き、人と違うことを自然なことだと思え、自分と世界とは繋がっているのだと感じることができる場所、つまりおとなとの間の安心できる居場所としての関係が大切なのだと説いているのです。
「ちがい」を「ちがい」として認めあい、受け入れあうこと、そのための前提には、自分自身が人から受け止められ、受け入れられ、安心していられる精神的な居場所が重要なのだということです。このことこそが、子どもたちに必要なことであり、それを求め、またそれが見守るのがセンス・オブ・ワンダーなのです。
そして、このセンス・オブ・ワンダーを子どもたちが発揮できる教育のあり方を考えるために、新教育ビジョンの策定では、主語の転換がおこなわれました。これまでは、教育行政の計画として、「わたしたちは」と書かれていても、それは教育委員会は、という意味に受け止められるような表現となっていました。しかし、この新教育ビジョンでは、明確に「区民」が主語になるような表現にすることとしたのです。区の教育の主役は子どもを含めた区民であり、教育行政はその主役の営みを支え、実現する基盤を整備するのだ、誰もが教育の当事者なのだ、という考えが明確にされたのです。
こうして、新教育ビジョンの基本的な枠組みがつくられていきました。これまでにない教育ビジョン、はじめから最後まで子どもと区民が主役になる教育ビジョン、こういうものが現実につくられていこうとしている。そういうワクワクする思いを強くしたのを覚えています。

次回は、この新教育ビジョンの具体的な内容について、ご紹介します。
\ 人生100年時代の社会のグランドデザインを描く/
\ 最新情報が届きます! /
牧野先生の記事を、もっと読む
連載:子どもの未来のコンパス
#1 Withコロナがもたらす新しい自由
#2 東日本大震災から学ぶwithコロナの中の自由
#3 Withコロナで迫り出すこの社会の基盤
#4 Withコロナがあぶりだす「みんな」の「気配」
#5 Withコロナが呼び戻す学校動揺の記憶
#6 Withコロナが再び示す「社会の未来」としての学校
#7 Withコロナが暴く学校の慣性力
#8 Withコロナが問う慣性力の構造
#9 Withコロナが暴く社会の底抜け
#10 Withコロナが気づかせる「平成」の不作為
#11 Withコロナが気づかせる生活の激変と氷河期の悪夢
#12 Withコロナが予感させる不穏な未来
#13 Withコロナで気づかされる「ことば」と人の関係
#14 Withコロナで改めて気づく「ことば」と「からだ」の大切さ
#15 Withコロナが問いかける対面授業って何?
#16 Withコロナが仕向ける新しい取り組み
#17 Withコロナが問いかける人をおもんぱかる力の大切さ
#18 Withコロナで垣間見える「お客様」扱いの正体
#19 Withコロナで考えさせられる「諦め」の怖さ
#20 Withコロナ下でのオリパラ開催が突きつけるもの
#21 Withコロナで露呈した「自己」の重みの耐えがたさ
#22 Withコロナであからさまとなった学校の失敗
#23 Withコロナの下で見えてきたかすかな光・1
#24 Withコロナの下で見えてきたかすかな光・1.5
#25 Withコロナの下で見えてきたかすかな光・2
連載:学びを通してだれもが主役になる社会へ
#1 あらゆる人が社会をつくる担い手となり得る
#2 子どもたちは“将来のおとな”から“現在の主役”に変わっていく
#3 子どもの教育をめぐる動き
#4 子どもたちに行政的な措置をとるほど、社会の底に空いてしまう“穴”
#5 子どもたちを見失わないために、社会が「せねばならない」二つのこと
#6 「学び」を通して主役になる
新着コンテンツ