
新納一哉さん、ゲーム開発にかける想い「やりたい気持ちに、ウソをつきたくない」
2020.07.29
子育て・教育
2021.04.30

この記事を書いた人
牧野 篤

東京大学大学院・教育学研究科 教授。1960年、愛知県生まれ。08年から現職。中国近代教育思想などの専門に加え、日本のまちづくりや過疎化問題にも取り組む。著書に「生きることとしての学び」「シニア世代の学びと社会」などがある。やる気スイッチグループ「志望校合格のための三日坊主ダイアリー 3days diary」の監修にも携わっている。

「読解力は人生を豊かにする。」私の友人で、もと高校の国語教師・村上慎一さんの言葉(村上慎一『読解力を身につける』、岩波ジュニア新書)です。読解力は、「人生」に直接かかわるものだとも、村上さんはいいます。
どういうことなのでしょうか。読解力は、日常生活に役に立つ実用的なスキルなのではないのか、そう思った方も多いのではないでしょうか。
さらに、数学者の岡潔は思想家・小林秀雄との対談で、こんなことをいっています。「文章を書くことなしには、思索を進めることはできません。書くから自分にもわかる。・・・・・・言葉で言いあらわすことなしには、人は長く思索できないのではないかと思います。」(小林秀雄・岡潔『人間の建設』、新潮文庫、35頁)
どちらも、読解力をはじめとする「ことば」の力は、人が生きるということの本質にかかわるものだといっているように聞こえます。
以前ご紹介した東ロボくんプロジェクトを主宰している新井紀子さんたちのグループが全国の読解力調査を行っています。それをもとに、新井さんは日本の子どもたちは世界的に見て高い学力を誇っているが、読解力を調べてみると、教科書レベルの文章がきちんと読めておらず、解答も設問を読まずに鉛筆転がしをして選択肢を選んだとしか思えないほどに正答率が低いと指摘しています。それは、この子どもたちが、新井さんのいう「AI読み」をしているからではないか、というのです。
「AI読み」とは、文章を文章として読まずに、単語を拾い読みして、勝手に意味を構成している読み方で、とくに「・・・・・・以外」とか、「・・・・・・のうち」という機能語と呼ばれる言葉が示している意味がとれないままになるので、掛かり受けなどが理解できず、誤読することになります。
この結果から、新井さんは人工知能が急速に発達し、社会に実装されていく近未来で、しかもすでに2030年にはその頃の大卒者の65パーセントがいまない職業に就き、47パーセントの職業が人工知能に代替されて、人を雇わなくなるといわれているのに、そしてすでに人工知能は、MARCHレベルの大学の学部入試に毎年8割の確率で合格するにまで発達しているのに、日本の子どもたちにこのような教育を施していて、彼らの未来は安泰なのか、と警告を発しています(新井紀子『AI vs. 教科書が読めない子どもたち』、東洋経済新報社)。
▶ 新井紀子『AI vs. 教科書が読めない子どもたち』東洋経済新報社
この議論には賛否両論さまざまにあることは知っています。それはもう、ネット上の議論を検索するだけでも、たくさんの意見が出てきます。それだけ、この本が提起した問題の社会的なインパクトは大きかったということでしょう。それについては、ここでお話しするつもりはありません。ただ、私には賛否両論どちらに対しても、違和感があるのも事実なのです。どちらも、とても表面的に読解力を、さらにいえば「ことば」をとらえているのではないかということです。
皮肉をいえば、たとえばApple社のCM「Think Different.」を取り上げて、新井さんの議論は、このCMでいわれているような個性を認めず、子どもたちを学校教育をはじめとするこの社会の枠組みに閉じ込めようとするものだ、それになじめない者を排除し、この社会のイノベーションを阻害するものだと批判する議論があります。
しかし、その議論はまったくdifferentではないように受け止められます。このCMは、これまで社会の異端者たちが、社会から排除され、忌避されながらも、この社会を変え、前に進めてきた、私たちは彼らは厄介者ではなく、天才だと考える。世界を変えられると信じて行動した者たちだけが、世界を変えられる、というメッセージが、それこそ厄介者で天才だったカリスマ経営者スティーブ・ジョブスの「ことば」によって語られています。
アップルCM「Think Different.」(声:スティーブ・ジョブズ)[日本語字幕]
ジョブスは、語っているのです。皆さんにわかるように。「ことば」によって。文法的にもしっかりとした彼の母語である英語を使って。そして、その内容は、極めて実用的であるように見えて、その実、think考えること、そしてdifferent違っていることを恥ずかしがるな、抑え込むな、それを恥ずかしいと思わせ、抑え込もうとする社会を、世界を変えろ、と人の本質的なことを訴えています。
考えること、違っていると意識すること、世界を認識すること、このことは違和感として感受されつつ、それが行動へと展開して、世界を変えるためには、その感覚や感情が、言語化され、自己意識として自分へと還ってこなければなりません。こういうことを、誰も指摘していないように思えるのです。Differentであるためには、thinkできなければならず、それはdifferentではない皆が使っている「ことば」を使わざるを得ない、という皮肉がここにはあります。
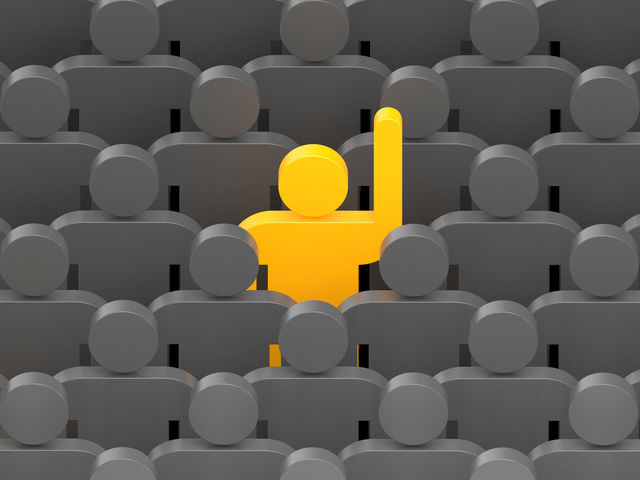
批判する論者には、新井さんのグループが行った読解力調査が、これまでの受験学力を肯定することにつながり、子どもたちの想像力と創造力を抑圧することになりはしないかと、危惧する人が多いように思われます。しかし、この人たちは、(意図的、無意図的を問わず)誤読も含めて新井さんの著作を読み、価値判断し、自分の意見を様々な媒体に、言語を運用して、文章として、書き、発言し、表明しているのです。
この人たちには、読解力は備わっています。読解力が備わっている人たちが、読解力をつけなければ、子どもたちの人生は人工知能に取って代わられてしまうという警鐘に、その読解力は子どもの個性を抑圧してしまうと、批判の声を上げているという、おかしな格好になってしまっています。
新井さんたちは、そういうことすらできない子どもたちがたくさんいることに対して、彼らの人生は大丈夫か、と問題を提起しているのではないでしょうか。
確かに、問題提起の仕方は、極めて実用的、つまり職業を人工知能に奪われてしまう、だから読解力をつけよ、読解力がついていれば大学入試もクリアできるという論理で書かれていると理解できる面もありますから、それが誤解を生んだということもあるかも知れません。また、人工知能の理解が、新井さん独特であるということも批判を招く一因になったのだろうとも思います。
しかし、ここで問わなければならないのは、受験学力の読解力であろうとなかろうと、冒頭の高校国語教師の友人の言葉にあるように、読解力は子どもたちの人生を豊かにするためにこそ必要なのだということの意味なのではないでしょうか。

この問題を考えるために、補助線として、サン=テグジュペリを取り上げてみます。『星の王子様』ではなくて、『人間の大地』(サン=テグジュペリ、渋谷豊訳『人間の大地』、茜文社)です。
この本の中でサン=テグジュペリは同僚パイロットのアンリ・ギヨメのエピソードを紹介しています。ギヨメは飛行機の墜落事故で遭難しますが、彼は零下40度にもなるアンデス山地を越えて、最後には救出されます。このとき、ギヨメは心が挫けそうになるたびに妻ノエルを思い浮かべて、気持ちを奮い立たせたのだといいます。ギヨメはこういいます。
「僕が一番苦労したこと、それは考えるのを止められないことだった。・・・・・・頭の中がタービンみたいに回転し続けるんだ。」「希望はまったくない。とすれば、これ以上苦しみつづけることに何の意味があるだろう?」(70—73頁)
意味にとらわれ、自分の生が無意味だと思えてくる状況下で、ギヨメがとった行動は、「救いをもたらしてくれるのは、一歩踏み出すことだ。一歩、また一歩。同じ一歩を繰り返して・・・・・・」でした。
そしてギヨメが救助され、仲間が奇跡だと涙にむせんでいるとき、彼が最初に発した言葉は、こうだったといいます。「誓ってもいい、僕がしたことは他のどんな動物にも真似できない。」
とにかく生き延びること。それが人の社会に対する責任なのだ。それは、生きなければならないかのようにして生きること、です。そしてその先には、サン=テグジュペリがいうように、人間であることの本質が指し示されることになります。
「人間であるということ、それはとりもなおさず責任を持つということだ。自分のせいではないと思えていた貧困を前に、赤面すること、僚友が勝ち取った栄冠を誇りに思うこと、自分に見合った石を積むことで、世界の建設に貢献していると感じることだ。」(76頁)
人間を動物と分かつもの、それは生きようとする意志であり、それを社会に対する責任であると自分を位置づけることであり、それはとりもなおさず、他者の存在を我が事として受け止められることだ、とサン=テグジュペリはいうのです。そして、それらすべてを人間に可能としているもの、それが「ことば」(の力)です。
▶ サン=テグジュペリ(著)渋谷豊 (翻訳) 『人間の大地』茜文社

それは、言葉ではありません。「ことば」です。私はこの二つの言葉を使い分けてきましたが、それはこういうことです。ギヨメがいう絶望的な状況におかれたとき「頭の中がタービンみたいに回転し続ける」こと、つまり意味を考えないではいられなくなる、すなわちなぜ自分はこんなに苦しまなければならないのか、自分の人生は何だったのか、という意味を問わないではいられなくなるとき、人は言葉を使って、その意味を考えています。
そこにはしかし、自分ひとりしかいないのではないでしょうか。自分の人生の意味、自分が苦しむ意味、自分がなぜこんな目に遭わなければならないのかという意味・・・・・・、なぜ自分が、なぜ、なぜ、なぜ・・・・・・、この自分に閉じられた意味の問い返しは、無意味という答えしかもたらしません。なぜなら、絶望的な状況におかれて、自ら生きる希望を失っているからです。
余談ですが、私は、『星の王子さま』で、最後、星の王子さまは絶望して自殺してしまった。それは、彼が社会の中に自分を位置づけることができなかったからだ(サン=テグジュペリ、河野万里子訳『星の王子さま』、新潮文庫)、彼の周りのおとなたちが、彼をきちんと受けとめなかったからだ、と解釈しています。
しかしギヨメが取ったのは、一歩足を進めること、妻・ノエルを思い、人間の社会に向けて一歩一歩、歩みを進めていくこと、それだけでした。それをサン=テグジュペリは「責任」だといいます。そこでは「ことば」(の力)が働いていたのではないでしょうか。意味などないのです。自分が生きる意味などない、あるのは、生きるという人間社会に対する責任、つまり自分を人間の中に位置づけて、他人事を自分事としてとらえ、自分がこの社会を担っている一員であるという自明なことを受け容れ、その一員としての役割を果たすこと、すなわち生き抜くこと、そのことが人間が人間であることなのです。
そして、そこでは「ことば」が自分を人間の中に生み出し、自分から人間が生み出されていきます。つねに、誰かとの間でその人を意識している自分を意識することで、自分に対する意識を「ことば」が与えてくれるのです。
▶ サン=テグジュペリ(著)河野万里子 (翻訳) 『星の王子さま』新潮文庫
「ことば」とは、自分を人間として人間の中から生み出し、人間の中に位置づける言葉です。
私たちは、新生児の時には、母胎の中で母親の声を聞き覚え、生まれてくると、聞き覚えた声を発する人に授乳を求める行動を取るといいます。その後、授乳してくれる人とまなざしの交換に入り、まなざしを交換しあう中で、命を預けているという信頼感とともに、言葉を獲得しようとして、その人に語りかけるようになります。生命の維持と「ことば」、そして信頼感が一体となって獲得されていくのです。

そこで獲得された「ことば」によって、私たちは自分に対する意識を持つようになります。私が信頼感を通して他者へと移行され、その他者から自分を見詰めるまなざしを獲得すること、つまり自己の他者である自己を生み出すことで、私たちは自己意識つまり自我を持つことができるようになります。ここで、自分を他者へと移行させることができるのは、すでに私たちが「ことば」を獲得し、「ことば」を用いて、他者との間に普遍的なかかわりをつくっているからです。
そして私たちは、その「ことば」を使って、自分を語り、社会を語って、社会を自分のものにしつつ、他者との間に「ことば」を介した関係をつくりあげていきます。それが、自分にとっての社会です。
私たちは、社会から生まれざるを得ず、そして社会をつくらざるを得ない存在なのです。私たちを社会から生み出し、私たちに社会を生み出させるのが「ことば」です。
つまり、私たちは「ことば」によって生み出され、「ことば」によって社会をつくり、「ことば」によって日々新たになっていく存在なのだといってよいでしょう。だからこそ、「ことば」を使うと、人と意思疎通できると思い、「ことば」によって理解し、理解され、「ことば」によってこの社会に位置づけを得ることができると思えるのです。
「ことば」とは、私たちそのものでありながら、社会そのものでもあるのです。
それだから、この「ことば」に躓くと、私たちの自分の存在が危うくなってしまいます。精神的な障害を抱えることとなるといってよいでしょう。いわゆる精神障害は、「ことば」の病なのだといってもよいかもしれません。そして、それだからこそ、「ことば」に躓くと、心理的なケアが必要となり、カウンセリングや心理的なセラピーが必要となります。
カウンセリングや心理的なセラピーでは、クライアントのことばをカウンセラーがオウム返しに返すことで、クライアント自身が再帰的に自らに対して「ことば」を用いる自己認識へと展開することで、クライアントの過去を再構成する、つまり現在起点の自己を過去からの連続として構成し直すことで、未来へと現在時点を移行させつつ、自己のアイデンティティを保つこと、すなわち自己の連続性を意識し、自己同一性を「ことば」で維持し続けることが可能になる構造をもっています。
それは、「ことば」による再帰性をクライアント自らのものとすることによって、クライアントの自己意識を自己参照という再帰性の連続へと接合して、クライアントのアイデンティティを一貫させることでもあります。
私たちは自分をつくり、自分であることを保つためにも、「ことば」が必要なのです。
たとえば、小坂井敏晶は徹底して近代社会の持つ主体という考えを解体しようとします。少し長くなりますし、小難しい話になりますが、概括してみます(小坂井敏晶『神の亡霊—近代という物語』、東京大学出版会)。
小坂井はこういいます。私たちが生きている社会、つまり近代の社会とは物語であり、装置に過ぎない。近代という社会は神を殺して、人間を主体として神から解放したが、しかしその結果、世界は無根拠であることを自らさらけ出し、私たちが現在ごく普通のこととして受け容れている人権や正義という近代社会の枠組みは根拠を失って、神の化身でしかなくなってしまった。しかも外部の権威であり、よすがであった神を否定してしまったために、因果を逆転させる形で、個人の内面、つまり主体を発明せざるを得なくなった。

責任つまり物事の原因を神が示してくれなくなったために、自由だとされる主体、つまり自己意識が発明され、正義が個人を根拠に、つまり権利として発明された。その基本は自由意志であり、そこから自己責任とメリトクラシーが生み出された。
そこではすべて、原因と結果が逆転し、偶然のなりゆきであったものに意志が組み込まれ、必然へと、つまりその人が意志を持って行ったがゆえに、その行為の責任はその人にあるとその人の責任を問い、原因は何であったのかと究明する歴史がつくりだされる。
人間は自由な存在であることにされ、意志を持つ存在だとされるが、意志とは身体運動を単なるできごとではなく行為だと認める社会判断であり、それは近代という認識の枠組みが導く社会制度であり、政治形態である。
本来、意志は事後的に判断され、主体は事後的に形成される、つまり行為の後でそれをやった者として認定されるのに、事態は逆転し、主体が意志をもって行動した結果、ある身体運動が行為としてなされたとして、責任を構成することになる。それが自由の本質となる。自由意志を持つからこそ、その行為はその意志の行使と見なされ、自由意志の行使にともなう責任が構成される。
つまり、個人に責任を負わせるために自由が発明され、意志が生み出されたのに、個人が自由な主体であるからこそ責任主体であるとして措定され、社会秩序の恣意性が隠蔽されて、人権や正義の正統性・正当性が保障される。
この議論はまた、個人のアイデンティティをめぐる議論だといってよいでしょう。小坂井は、近代社会は、神を殺した結果、外部の帰責主体を失い、内部に自己という意志を持った主体をつくりださなければならなくなった、その結果、個人を基本とする人権や正義の観念が生み出され、その正統性と正当性が個人が自由な責任主体、すなわち意思を持つ存在であることによって担保されることとなったというのです。
そして、ここに「ことば」が介在しているのです。この意志を持つ自由な責任主体である個人という設定は、アイデンティティを構成している言語、つまり「ことば」のありようと深くかかわっています。それはつまり、先ほど述べたように、カウンセリングや心理セラピーにおいて、クライアントのことばをカウンセラーがオウム返しに返すことで、クライアントの過去を再構成して、アイデンティティを保つこと、つまり自己同一性を「ことば」で維持し続けることが可能になることと同じ構造をとっています。
私たちは飽くまで「ことば」によってつくられているのです。そしてだからこそ、「ことば」が曖昧になったり、うまく身についていなかったり、うまく用いられなくなったりすると、自分の存在が曖昧になり、社会に居場所がなくなって、虚無感に苛まれることとなります。そこでは、「ことば」は言葉になってしまい、主体の意味を問い始めます。
またそうだからこそ、言葉は他者を傷つける武器にもなってしまいます。いじめなどはその最たるものですし、いじめによって自殺を招くことになってしまうのも、言葉が凶器となるということでしょう。その言葉は「ことば」ではありません。

では、こうして「ことば」でつくられる私という存在は、「ことば」によって語り尽くされることで、消えてしまうものなのでしょうか。しかし、それがそうではないのです。
私たちは、「ことば」を使って自分のことをいおうとすると、どうひっくり返っても、自分のことをいい切ることはできません。つねに何かが残ってしまうような感覚、それはまたある種の物足りなさという欠損感でもあるのですが、そういうものが残ってしまいます。それは、私たちが自分を「ことば」によってつくるときに、その「ことば」の前に、自分では「ことば」では表現できない「からだ」を持っているからです。

私たちは、「からだ」を持って生まれることで、また産み落とされることで、その「からだ」が「ことば」を学んで、「ことば」で自分をつくるようになっています。「ことば」つまり自己意識の前にあるのは、「からだ」であり、さらに後から「ことば」によって表現されることになる感覚です。
だから、私たちは、いえることしかいえない、のですし、いえることを後からしかいえない、のです。私たちはつねに遅れて生まれてくるのです。
そして、「ことば」は本来社会のものであるがために、それを私が私の「からだ」において身につけることで、それは私の「からだ」によって少しずつズラされていってしまいます。私たちは、たとえば、痛いといいう感覚を「イタイ」と表現して、他者と痛みを共有することはできますが、その他者の痛みを直接感じることはできません。でも、「イタイ」という感覚を自分が持つことで、それは見ず知らずの人との間で、痛みを共有することにつながります。
それでも、その痛みとは、「ことば」によって表現された痛み、つまり普遍的で抽象的な痛みでしかありません。その痛みを「イタイ」感覚を通して、自分の「からだ」につなげるときに、「イタイ」という「ことば」は、少しずつズラされながら、私の「からだ」において具体的な像を結ぶようになります。
それはいわば、「ことば」を持つ社会において、それを用いる「からだ」の多重な重なりにおいて、社会の混沌の中から意味が立ち上がり、「ことば」が他者との間で紡がれることによって、その重なりとズレにおいて社会における意味が豊かに形成され、社会がつくりだされていくという運動に他なりません。
それだからこそ、「ことば」が曖昧になると、私たちは「からだ」の置き場がなくなって、「からだ」自身の固有性、つまり誰にも渡すことのできない自分だけの感覚にすがるようになります。それが、いわば身体の強度というものです。そしてそれが、アディクションにつながります。つまり身体を痛めつけたり、薬物に依存したり、性的な興奮に溺れたり、そうでなければ社会から「からだ」を引き上げようとして、精神を病んだりするようになってしまいます。
ずいぶんと難しいことをこねくり回しましたが、これが、新井さんたちの読解力と人工知能をめぐる議論への様々な意見に対する私の違和感のもとなのです。
読解力を単なる実用的な言葉の運用だととらえてしまうと、それは役に立つ/立たないという狭い議論に終始することとなってしまい、それは端的に受験に役立つ/役立たないという議論に回収されてしまいます。その限りでは、批判する論者の意見は正しいのかも知れません。
しかし、その論者自身が、きちんと「ことば」を使って、新井さんの文章を読み、その意味だけでなく、行間を読んで、意図を読み取り、自分の考えと対話させた上で、自分の論理を文章として書き出し、発表しているのです。その人たちの読解力とそれを支えている「ことば」の力はたいしたものなのではないでしょうか。
ところが、自分がそういう高度な「ことば」の運用を、この社会において行うことで、その「ことば」を新たな「ことば」へとズラし、つまり創造し続けることで、自分をこの社会へと新たに生み出し続けているにもかかわらず、その論者たちは、そのことを意識せず、読解力を実用性のレベルで、つまり自分が運用している「ことば」のレベルとはかなり異なる、いわば低いレベルで読解力を議論しつつ、現実には子どもたちから読解力つまり社会に自らを位置づける「ことば」の獲得と運用を否定するかのような論理を構成しているのです。このことに、私はある種の危惧を抱きます。
そのような「ことば」の運用つまり実用的な運用では、子どもたちの存在をこの社会にきちんと位置づけることはできず、その存在そのものを実用的なもの、つまりたとえば経済的な道具である労働力や消費者というレベルでしか理解しようとしないという、人間観の貧困を招いてしまいます。それはいいかえれば、子どもたち自身が自分をそのようにとらえ、社会に位置づけ、そしてその社会において役に立たなくなるという恐怖心に強迫されて、さらに「ことば」を実用的に言葉ととらえることで、その「ことば」は彼ら自身の存在そのものとはかかわりのない、表層的な意味を問う言葉へと矮小化されていってしまうことを意味しています。私はこのことを怖れるのです。
そのような言葉に、一人ひとりの子どもたちの人生を励ます力などありません。それはせいぜいギヨメのいう自分の意味だけを問う言葉であるに過ぎません。自分を社会の中でつくりだし、社会を担う「ことば」にはならないのです。
そしてもうひとつ重要なことがあるのです。「ことば」がこのような「ことば」であるためには、私たちが「からだ」において、そのような「ことば」を身につけることができるだけのしっかりした信頼感のある関係の中におかれていて、その信頼感とともに「ことば」が学ばれ、「ことば」を発することで自分を受け止めてもらえ、わかってもらえるという期待や予期が生まれなければならないのです。

それがないままに「ことば」が学ばれると、それは自分だけの言葉へと矮小化されてしまい、それは自分を社会に位置づけ、また社会をつくる自分として自分を生み出すことができなくなってしまいます。自分という存在が、実用的な道具になってしまうのです。そこでは、意味や意義が問われ、それがなくなることが、その人の社会的な死となってしまいます。
このような「ことば」を身につけることができる関係とは、相互の承認関係であり、その承認関係はまた「ことば」によって支えられているものでもあります。私たちには、子どもたちとの間にこうした承認関係を築き、彼らが「ことば」の担い手となるように励まし続けることが求められているのだとはいえないでしょうか。
Withコロナの時代のオンライン生活で、私たちは改めて「ことば」の重要性と脆さを思い知らされたのではないでしょうか。それはまた、単に画像が見えればよいとか、オフラインの対面で教育を行った方がよいというような議論とは異なる次元の、もっと深い議論が私たちに求められていることを示しています。
\ 人生100年時代の社会のグランドデザインを描く/
\ 最新情報が届きます! /
牧野先生の記事を、もっと読む
連載:子どもの未来のコンパス
#1 Withコロナがもたらす新しい自由
#2 東日本大震災から学ぶwithコロナの中の自由
#3 Withコロナで迫り出すこの社会の基盤
#4 Withコロナがあぶりだす「みんな」の「気配」
#5 Withコロナが呼び戻す学校動揺の記憶
#6 Withコロナが再び示す「社会の未来」としての学校
#7 Withコロナが暴く学校の慣性力
#8 Withコロナが問う慣性力の構造
#9 Withコロナが暴く社会の底抜け
#10 Withコロナが気づかせる「平成」の不作為
#11 Withコロナが気づかせる生活の激変と氷河期の悪夢
#12 Withコロナが予感させる不穏な未来
#13 Withコロナで気づかされる「ことば」と人の関係
#14 Withコロナで改めて気づく「ことば」と「からだ」の大切さ
#15 Withコロナが問いかける対面授業って何?
#16 Withコロナが仕向ける新しい取り組み
#17 Withコロナが問いかける人をおもんぱかる力の大切さ
#18 Withコロナで垣間見える「お客様」扱いの正体
#19 Withコロナで考えさせられる「諦め」の怖さ
#20 Withコロナ下でのオリパラ開催が突きつけるもの
#21 Withコロナで露呈した「自己」の重みの耐えがたさ
#22 Withコロナであからさまとなった学校の失敗
#23 Withコロナの下で見えてきたかすかな光・1
#24 Withコロナの下で見えてきたかすかな光・1.5
#25 Withコロナの下で見えてきたかすかな光・2
連載:学びを通してだれもが主役になる社会へ
#1 あらゆる人が社会をつくる担い手となり得る
#2 子どもたちは“将来のおとな”から“現在の主役”に変わっていく
#3 子どもの教育をめぐる動き
#4 子どもたちに行政的な措置をとるほど、社会の底に空いてしまう“穴”
#5 子どもたちを見失わないために、社会が「せねばならない」二つのこと
#6 「学び」を通して主役になる
新着コンテンツ