
【張り子作家・アート大福さん】絵本のように可愛く不思議な世界。まったくの未経験から独学で作家活動をスタート。「私にもできる!」と思ってほしい
2024.02.20
子育て・教育
2020.11.10

この記事を書いた人
牧野 篤

東京大学大学院・教育学研究科 教授。1960年、愛知県生まれ。08年から現職。中国近代教育思想などの専門に加え、日本のまちづくりや過疎化問題にも取り組む。著書に「生きることとしての学び」「シニア世代の学びと社会」などがある。やる気スイッチグループ「志望校合格のための三日坊主ダイアリー 3days diary」の監修にも携わっている。

学校には社会の巨大な慣性力が働いています。とくに、これまで述べてきたように、社会が学歴社会化し、人々が学校を利用して、その生活の向上を実現しようとする社会では、学校を変革することはとても困難です。
その社会では、また高学歴であること、さらには難関校に進学することが、社会的に意味があること、価値があることとされますから、人々は人そのものを学校的な価値で測って、相互に比べることになります。
ですから、難関校に進学した子どもの方が、人格的に優れているかのような観念に、人々は囚われてしまいます。そして、確かに、学歴社会をつくっている工業社会は、そういう観念に覆われた社会でもありました。
画一化と均質化、これが工業社会の特質です。つまり、自然や人々の日常から隔離された均質な空間と画一的な時間が支配する「場所」、これが社会としてつくられていくのが、工業社会です。どこに持っていっても、同じ生産ができる空間つまり工場と、どこであっても同じ速さで一方向に流れる時間、つまり時計時間がそれです。
そのような社会では、人間も一人ひとり異なる存在ではなくて、「労働力」という働ける能力をもった一般的な人間として想定され、その能力を用いて働くことで、この社会の価値、つまり利潤をもたらすものとされます。
そして、その働くという営みも、誰もが同じように働けるように単純労働の寄せ集めとして生産工程がつくられていきますから、労働の質に違いはなくなってしまい、結果的には量つまり時間で計られることとなります。
ですから、たとえば同じ時間単価でも、一生懸命働いているあなたと、監督の目を盗んで怠けている彼とで同じなのは、そこでは働いていることの質によって労働力が評価されているのではなくて、誰もが同じ労働力を持っていることを前提で、それを1時間支出しているから、それに対してその対価を支払うという計算が成り立っているからです。
労働に対して賃金が支払われるのではなくて、労働力という誰もが持っている能力に対して、その使用料が支払われているのです。 このような人間観は、これまでの工業社会では、社会のあらゆる面に見ることができます。その典型が、学校です。その前提は、子どもたちは誰でも学ぶ力を持っていて、誰でもが、同じ内容を、同じように学んで、同じように成長・発達することができる、という人間観です。
ですから、子どもたちは、日常生活から切り離され、しかも自分では選ぶことのできない生まれや階層・階級、宗教、両親の思想信条や職業などから切り離された、均質で世俗的な空間であり、画一的な時計時間が流れる「場所」、つまり学校に組み込まれて、それら自分では選べない様々な条件をなかったことにして、いわゆる普通教育、つまり宗教的な価値その他にとらわれない、客観的な知識を教えられることで、学校の成績だけで、将来を決めることができるとされました。
子どもの人生は、あらかじめ決まっているものではなくて、学校における成績のみが左右する、後天的なものだとみなされるのです。

でも、実際には成績には違いがあります。どの子もみんな同じ質の子どもで、同じく学ぶ力を持っているのに、そして誰にも平等に学校に行く機会が与えられていて、同じ教育内容を、免許を持った教師が教えていて、しかも学校によって教師が偏らないように、定期的な人事異動まであって(余談ですが、学校の間を教師が定期的に異動する制度は、世界的に見て、あまり一般的ではありません。多くの国では、教師は学校採用であり、その学校の教師として働くのですし、異動も、基本的には他の学校からスカウトされたり、公募があって採用されたりしたときです。まるで、いまの日本の大学のようです)、平等を保障しているのに、その上、学校の施設や設備も全国一律の基準があって、全国津々浦々ほとんど同じなのに、それでも成績が違う。
なぜなのか。ここまで平等、画一、均質なのに、そして子どもたちも均質で同じ能力を持った子どもなのに、なぜ異なるのか。もう、違いは一つしかない。それは、やる気が足りないからだ、がんばりが足りないからだ、ということになります。
そうなると、成績がよくないのは、がんばりが足りないからだ、やる気がないからだという、その子の人格にかかわる問題となってしまいます。いいかえれば、その子は、勤勉ではないとみなされるのです。
こうして、学校の成績がその子の人格評価につながってしまい、より難しい上級学校に進学した子は、がんばった子だ、勤勉な子で、人格的にも優れているからだ、ということになります。
これも余談ですが、産業を示す英語のindustryは、実はもともとは勤勉という意味なのです。それが転じて、産業とくに工業を示すようになりました。いかに工業における労働、つまり工場労働が勤勉を求めているのかがわかります。
しかも、ここでも均質な人間観が作用します。誰もが同じ人間なのだから、誰もががんばれるはずだ。だから、がんばろう、がんばって成績を伸ばそう。そうすれば、自分の人生は学校を通して、よりよいものになるはずだ。こういう観念が、学校を支配します。
先生方も、だからこそ、子どもたちにがんばることを説き、がんばって勉強しようとお尻を叩き、「クラスのみんなが100点取れるまで、一緒にがんばろう」などといって、子どもたちを励ますようになります。
がんばることが、社会的な価値になっていくのです。そうなると、家庭そのものが、子どもたちにがんばることを求め、「勉強、がんばっていらっしゃい」などと、子どもを送り出すようになります。
がんばることで、向上する。これが、社会の価値となるのです。それはまた、コツコツと勤勉に、という工業社会の価値観と重なっています。そして、その裏には、コツコツと勤勉にがんばれば、会社が大きくなって、国の経済が発展して、収入が増えて、自分の生活が豊かになって、よりよい生活が送れるという、発展という観念が貼り付いていました。
それは、端的には物質的なものが増える、つまり規模が大きくなって、経済が発展する(GDPが拡大する)、その結果、賃金が増えて、ものが豊かになる、というような、測れるものが大きくなっていくという感覚です。
そして、この発展という感覚は、子どもの成長・発達という感覚と表裏のものです。子どもたちの身体が大きくなっていくこと、働けるようになることや、子どもたちの知的能力が高まって、よりよい労働に就くことができること、こういう時系列に沿った、大きくなることやよりよくなっていくという変化の感覚が、発達としてとらえられ、それが工業社会の一面的な拡大、つまり規模の発展とのアナロジーで理解されることとなるのです。
しかも、その子どもたちは、成長・発達して、学んで能力を向上させることで、現役世代を乗り越えて、この社会をさらに発展させる原動力になる、と期待されるのです。
このことの裏返しが、退職者や高齢者に対する見方です。彼らは、すでに終わった人、役に立たない人、価値がなくなった人という感覚が広がることになります。
「老後」という言葉も、現役から引退した残りの時間という意味でしょう。そして、老いることが否定的な価値を帯びることになり、若々しくて、発達し続けることが、価値あることとなります。まるで、自己増殖し続けることが目的である資本と同じような感覚が、人々を支配するようになるのです。
このように発達が社会的な課題となることで、子どもを対象とした学問がそれこそ発達するようになります。教育学や心理学です。そして、そこでは発達そのものが人間の本質であり、誰でもが発達する存在なのだということが強調されることになります。
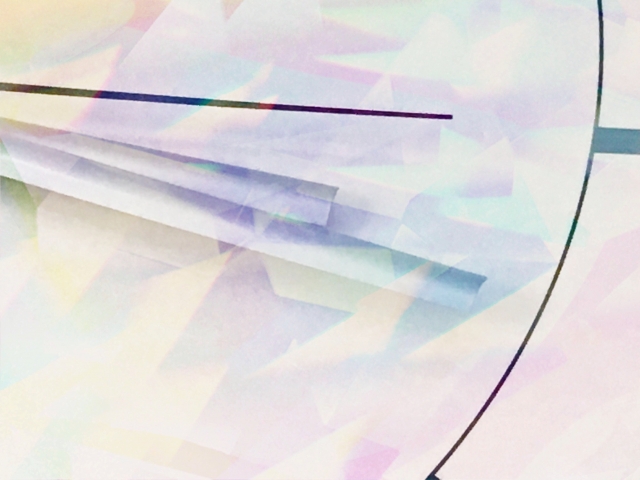
私は大学生の頃に、このことにかかわって、いまでも鮮明に記憶に残っている授業での体験があります。心理学の授業に出ていたときでした。先生が、子どもの発達を示すのに、次のようなたとえを用いたのです。
子どもたちの中には、時計の秒針のように、目に見えるかのようにして早く発達する子どももいれば、長針のように発達する子もいる。そして、短針のように、じっとしていて、ほとんど動かないかのように見えて、しっかりと発達の歩みを刻んでいる子もいる。それぞれに速さは違うけれど、子どもは誰もが発達する。これこそが人間の本質なのです、と。
発達は人間普遍の本質で、誰でもが発達する、そこに違いはない。この麗しい話を聴いて、私にはある疑問が浮かんできました。そこで、質問してみたのです。「先生のおっしゃる時計の文字盤は一枚しかないのですか」と。すると、この先生はとても誠実な人で、こうおっしゃるのです。「そうなのです。残念ながら一枚なのです。」
私は、「残念ながら」に引っかかってしまって、考え込んでしまいました。「なぜ、残念ながらなのか」とあれこれ考えているうちに、授業が終わってしまいました。
それで、先生を追っかけて研究室に行って、質問を続けたのです。「なぜ、残念ながら一枚なのでしょうか」と聞き直したら、先生は、こうおっしゃるのです。「いえね、本当に残念ながらなのです。いろいろな尺度があっていいとも思いますが、一枚にしておかないと、測れないでしょ。この一枚でなくても、他の文字盤を使えば、他の速さが測れるかも知れませんが、それでもその文字盤は一枚でなければなりません。そういうことです。」
私はそこで、ハッとしたことを覚えています。私は、この先生の授業を聴いて、文字盤はいろいろあってもいいのではないのか、そうすれば、遅いとされていた子も早いとされるかも知れないし、早いとされていた子は遅いとされるかも知れない。それぞれがそれぞれの文字盤を持っていてはなぜいけないのか、と考えていたのでした。しかし、先生がおっしゃるのは、そういうことではないのです。
発達というものが本質である以上、それは発達として測れなければならず、それが本質である以上、誰にでも同じ尺度があてがわれなければならない。逆にいえば、測れるから発達が本質だと見出されることとなったということだ。そういうことなのだと、思い至ったのです。
しかも、発達を本質とみなして、だからこそ人間は皆同じなのだ、人間としての本質は変わらないのだというこの人間観は、障害を持った子どもたちでも発達しているのだという知見をもたらすことで、障害児までをも発達を基本とした均質な人間観の中に回収してしまうほどの力を持ったものでした。
それまで、人間は誰もが同じで、平等なのだ、だから差別なんてあってはならないのだと美しい理想に浸っていた若者にとって、それはショックでした。
しかし、この発達にもまた違いが出てきます。発達が早い子と遅い子がいることは明らかだからです。測ることができるから、比較することができるようになるのです。
そしてこの違いをも、学校的な理想は、誰もが発達するのだから、それが人間の本質なのだから、誰もが発達できるはずだ、それができないのはがんばりが足りないからだ、として、またしてもがんばることを求め、がんばることに回収しようとします。
この議論はさらに、がんばってもできなければ、仕方がない、がんばることそのものが大事なのだ、という話に横滑りしていってしまいます。いわば精神論と発達が結びついてしまうのです。
しかも、それが功利主義と結びつくと、学校でよりよい評価を得るためには早くから発達することが望ましい、とばかりに、早期教育・能力開発が保護者の心をとらえるようになり、少しでも早くから、他の子よりも少しでも早く、が一つのトレンドとなってしまいます。その行き着いた先が、胎教なのかも知れません。

こうして、徹底的に均質化することで、一つの尺度で測ることができ、それを数字化、つまり時計の文字盤のように数字で表すことができるようになる、すなわちすべての質は量で表すことができるようになって、その量の違いがそれぞれの子どもの違いなのだという知見がもたらされるようになります。こうして、お互いに比べることができるようになります。しかも、この量は、がんばれば増えるというのが学校の信奉する価値です。
あらゆることが、人間としての本質までもが、同じであり、それを同じように扱っているのだから、ある時点での量的な違いは、その子のがんばり、努力の違いとして、解釈されることになります。
これはとても怖いことなのではないでしょうか。つまり、たとえば学校の成績はその子のがんばろうとしたり、努力しようとしたりする気持ちの違いや、実際に努力した結果だと解釈され、それはつまるところ人格を評価することにつながってしまうからです。
そうすると、子どもにしてみれば、学校の成績がよくないということは、自分の人格が低く評価されてしまうことと同じになってしまいます。そして家庭が子どもの成績に一喜一憂すればするほど、しかも保護者として子どものことを心配すればするほど、子どもにとってみれば、お父さんお母さんは成績がよい子が好きなのだ、成績がよくない自分はダメな子なのだという感覚をもたらすことになってしまうのではないでしょうか。
ところで、このところ格差論が再び人々の耳目を集めているように思います。社会の階層格差が広がっていて、階層間の移動が硬直化しているという議論です。
そこにはまた、「子どもの貧困」が目に見える形で社会問題化しているなどの社会現象もありますが、長期にわたる不況で、家計が年々豊かになるという感覚を持てないでいる人々の肌感覚のようなものもあるのではないでしょうか。
この問題に対して、社会的な経済階層は学校によって世代間で再生産されるという議論があります(たとえば、ボウルズ=ギンタス『アメリカ資本主義と学校教育—教育改革と経済制度の矛盾』(1)(2)、宇沢弘文訳、岩波書店)。
ボウルズ=ギンタス『アメリカ資本主義と学校教育—教育改革と経済制度の矛盾』(1)(2)、宇沢弘文訳、岩波書店
これは、社会学や教育社会学などの研究で明らかになった知見で、根強い支持があります。最近では、貧困は学校によって世代間で再生産されるという議論もあります。
つまり、学歴社会においては、経済階層が低いと、子どもに高い学歴を保障することができず、子どもが低い階層にリクルートされてしまい、またその孫が同じようなルートをたどることになるという議論です。
この議論にかかわっては、社会階層と移動に関する調査研究が1955年から大規模に進められていて、約60年間の調査結果の蓄積があります(SSM調査)。この調査は、社会階層を上層ホワイトカラー層(専門・管理)・下層ホワイトカラー層(事務・販売)・自営業・農業・上層ブルーカラー層(熟練ブルーカラー)・下層ブルーカラー層(半・非熟練ブルーカラー)の6つの階層に分けて、父親から息子への世代間階層移動のパターンを分析しようとするものです。
これを60年間にわたって再度検討し直したところ、結論だけ申し上げれば、日本社会は1990年代後半に入ってから、とくに不平等化が進行したわけでもなく、1950年代から2000年代にかけて、出身階層間の移動の機会の格差はほぼ安定していること、また現実にどの階層からどの階層へと移動しているのかを調べると、経済構造の変容によって、60年間では、全体として移動率が増え、上層ホワイトカラー層への移動が増えていることが見て取れるといいます(石田浩「世代間移動からみた社会的不平等の趨勢—JGSS-2000 にみる最近の傾向—」『JGSS研究論文集』[1]2002年など)。
この二つの知見を、私たちはどう受け止めればよいのでしょうか。実際に、学校を通して社会的な階層が再生産され、格差が拡大しているという議論があり、そしてそれは人々の肌感覚にも合ったものとして受け止められています。
反面で、実際の世代間の階層移動は、とくに近年、世代間の階層移動のしやすさが狭まったわけではなく、高度経済成長期から60年間一貫して、安定している。しかも、経済構造が変容することで、いわゆる自営業や農業さらには製造業の雇用が縮小する中で、全体としては上層ホワイトカラーへの移動が増えている、つまり階層上昇している。こういう知見もあるのです。
私たちの肌感覚は、単なる感覚であって、実際には階層移動のしやすさが狭まったわけでもなく、また実際にも上層への移動が増えている。こういうことなのでしょうか。
しかし、所得再分配の偏りを示すジニ係数という数字を見ると、当初所得分配で1980年代に0.4ほどだったものが、いまや0.6近くになっていますから、確かに所得の格差は広がっているのです(ジニ係数は、所得の分配の偏りを示すもので、まったく平等に分配されていると0.0に、ひとりの人が独占している状態だと1.0になるように計算し、0から1の間の数字で示されます)。
ただ、これも税金や社会保障などで調整したあとの係数を見ますと、1980年代から最近までを見ても0.3強から0.4弱を推移していて、さらに当初分配が急激に拡大している2000年代に入ってからは、0.4弱でほとんど変わらず推移していますから、社会保障による再分配が所得格差を減らすのに重要な役割を果たしているといえます。
具体的には、2017年の当初所得ジニ係数は0.5594でしたが、再分配所得ジニ係数は0.3721となっています。(厚生労働省政策統括官『平成29年所得再分配調査報告書』)
しかしこれも、社会的な再分配が強化されると、昨今のような超高齢社会では、高齢者福祉への負担が現役世代に回されることになりますので、世代間の不公平感が強まることにもなってしまいます。このことは、年齢別のジニ係数に示されています。
2011年の数字で、65歳以上の高齢者では、再分配所得ジニ係数が当初所得ジニ係数よりも大きく改善されており、社会保障費が高齢者に回っていることを示す反面で、2008年と11年を比べてみると再分配所得ジニ係数が40歳以下と50歳から69歳で大きく増加していること、つまり再分配所得の開きが出てきていて、現役世代の負担感が増していることがうかがえます。
(厚生労働省政策統括官、上掲。なお、65歳から69歳で再分配所得ジニ係数が増加していますが、それは65歳以上になっても働いている人がいて、その人たちに年金が支給されることで、働いていない人との間で格差が開いているためだと思われます。ですから、その人たちのほとんどが退職する70歳以上になると、再分配ジニ係数は縮小します。)
また、再分配所得ジニ係数が当初所得ジニ係数よりも約3割改善されているとはいっても、先進国グループであるOECDの平均よりは高い数字です。
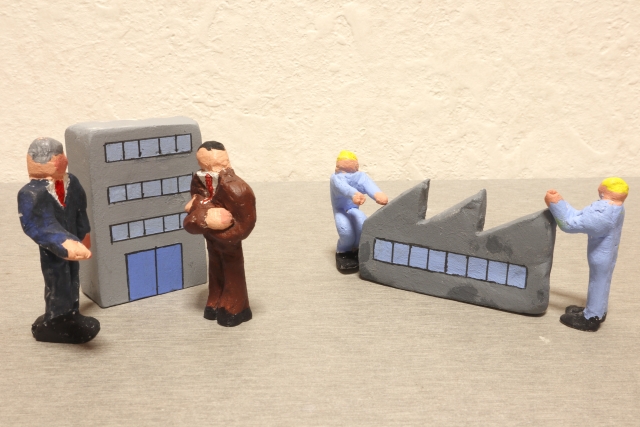
この結果が示すのは、肌感覚としての格差の拡大は、学術的な根拠のないものだということなのでしょうか。このように考えると、高度経済成長期に、人々の肌感覚では格差が小さくなっている、さらにバブル経済真っ盛りの頃に一億総中流とまでいわれたことも、実はそうではなかったということになります。しかし、本当にそうなのでしょうか。
肌感覚というのはとても大切だというのが、私の個人的なそれこそ感覚です。この肌感覚として格差が小さくなり、みんなが中流になった、そしてその後、格差が広がっているという感じは、階層移動と関係があるのかと問い返してみてはどうでしょうか。
たとえば、1990年代後半からの格差拡大について、階層移動のしやすさから見たら、統計的にはそれまでの50年間とほぼ変わらないという結果が出ています。
しかし、人々が格差が拡大したと感じてしまうのはなぜなのか、ということを考えると、経済的な不況や産業構造の変容によって、いわゆる上層において経済的なパイの縮小が起こって、競争が激化し、上昇移動率が減って、逆に下層において非正規雇用などが増えて、雇用のパイの拡大が起こっていて、下降移動率が増えているという結果がそうさせているのだとはいえないでしょうか
(たとえば、石田浩・三輪哲「階層移動から見た日本社会—長期的趨勢と国際比較—」、『社会学評論』第59巻第4号、2009年)。
これは、相対移動率と絶対移動率という移動率のとり方とかかわっています。相対移動率とは、社会経済構造の変動に関係なく、世代間でおこる社会階層の移動を示します。絶対移動率とは、社会経済構造の変動の影響によって生じる世代間の階層移動をいいます。
これをみると、相対移動率は一貫して変化がなく、日本の社会は、階層移動がしやすくも、しにくくもない社会だと一般にはいわれます。しかし、絶対移動率を見ると、高度成長期には農業から都市のホワイトカラー・ブルーカラー層へ、さらにブルーカラー層からホワイトカラー層への移動が見られ、1990年代のバブル経済崩壊後は、自営業からホワイトカラー層への移動が見られ、近年では、上層ホワイトカラー層から下層ホワイトカラー層へという下降移動が増えているといわれます。(石田・三輪、上掲論文)しかも、上層ホワイトカラー層内部では、競争が激化しています。
これが肌感覚をつくっているのではないでしょうか。そしてこのことを考えると、人々が肌感覚で、格差が広がっていて、社会は不平等となっていると感じるのは、産業構造が高度化して、安定する反面で、少子高齢化の中で市場が縮小する社会に入ったこと、しかも従来のような製造業中心の工業社会から、情報やサービスを基本として、いわば営業や事務を基本とする下層ホワイトカラー層中心の大衆消費社会へと社会の構造が組み換えられたことによって、学校が糊の役割を果たして表裏をなしていた、社会経済の拡大・発展と家計の向上いう宿命が果たされなくなったからではないでしょうか。
このことは、社会経済構造の変動に影響を受けないで、常に上層を占め続ける人々と常に下層にしかいられない人々の間で、常に社会経済状況の影響を受ける大量の人々がいるということですし、その人々は階層移動をしなくても、家計の向上という観点からは、常に不安定な状態におかれているということなのではないでしょうか。
こう考えると、学校を経由することでもたらされる「出世」とは、一体どういうことであったのかを改めて考える必要が出てきます。
一般庶民にとっては、「出世」とは階層の上昇ではなくて、上昇した結果、であり、または階層上昇しなくても、その結果であることがもたらされれば、それでよかったのではないのでしょうか。その結果とは家計の向上、つまり「おカネ」です。
たとえば、私の例を挙げます。私の父は、戦前の昭和一桁世代で、戦争中には勤労動員で取られ(間一髪で少年兵として志願しているところでした)、戦前の尋常小学校しか卒業しておらず、戦後はたたき上げの技師として、大手自動車メーカーで働き、働きながら夜間中学と高校さらに大学に進学していますが、社内学歴としては尋常小学校卒業でした。
それでも、その会社の急成長期にあたることで、管理職に就いています。いわゆるモーレツ社員の走りです。祖父は、明治30年代生まれで、田舎の鉄工場の熟練工で、尋常小学校卒です。そんな家庭に、私は高度経済成長期に生まれ、経済成長の波に乗ってひとしなみの物質生活を享受するサラリーマン家庭の経済力に支えられて、大学院にまで進学し、バブル経済がはじける直前に大学に職を得て、現在に至っています。
絵に描いたような「出世」物語ではないでしょうか。口癖のようにして父がいっていた言葉があります。「サラリーマンには土地や資産は残してやれない。残せるのは学歴だけだ。行きたいところまで行かせてやるから、がんばって勉強しろ。」これが、庶民の肌感覚だったのではないかと思います。
そしてその背後には、「力もないのに」(とは、父の愚痴です)自分を追い抜いて社内で出世していく高学歴者に対するある種の悔しさのようなものが貼り付いていたのだと思います。

しかしこれは本当に、社会階層の上昇による家計の向上が達成されていたことを意味するのでしょうか。確かに高度経済成長期には、より高い学歴を得ることが、より高い階層へと移動して、高い所得を手にする手段のように思われていたのだと思います。しかし、それは上層のパイつまりポストが拡大していて、下層から人がどんどん補充された時期の特異な現象だったのではないでしょうか。
そのことは、私の次の経験からもいえることです。たとえば、私の初任校は旧帝大系のそれなりの難関校です。しかし、バブル経済がはじけ、しかも企業内がICT化を進めることで、大量の余剰人員を抱え込んだ結果、私の教え子たちはある時を境に、突然、職がなくなってしまいました。
就職氷河期です。そしてその反面で、その時期に急激に増えたのが、いわゆる非正規職であり、流動的な雇用でした。その頃から、いわゆる日本型雇用が解体し始めたといわれ出します。そして、さまざまなベンチャー企業が立ち上がり始め、転職市場が拡大し、労働力の流動化が推し進められることとなります。
また、私たちが大学を卒業して就職する頃には飛ぶ鳥を落とす勢いだった銀行なども、この時期の長期不況で合併と従業員のリストラを繰り返すようになり、私の同級生にも社内でストレスを抱えて、精神を病んだり、耐えきれなくて退職したりした者が大勢います。転職した者の多くが下降移動でした。
それまでの社会を構成していた階層性が徐々に崩れ、社会が流動化していく中で、その中でも上層を維持し得る階層を除いては、絶対移動率が高まる社会がやってきているのではないでしょうか。
そして、それを裏返せば、高度成長期にあっても、私の家庭のように、経済構造の変容の波に乗れた人々は、それなりの恩恵を受けられましたが、それはまた経済構造が次のあり方へと変わることで、不安定化するものなのかも知れないということです。
そして、父がいみじくもいっていたように、「子どもに残してやれるものがないサラリーマン」にとっては、学歴は「出世」ではなくて「家計」の保障だったのではないでしょうか。そこで求められていたのは、「出世」ではなくて、「出世」することで得られる資産であり、家計の向上なのであって、それは端的に「おカネ」だったのではないでしょうか。
このようにとらえると、みんなが功利主義的に学校をとらえて、学校を経由して、就労し、家計を向上させようとしましたが、それは、出世するからではなくて、また階層を上昇するからではなくて、むしろ会社に就職すること、都市に移動することが、収入の拡大をもたらすことでもあったという、日々物質的に豊かになるという現実の実感によって、実現したと受け止められていた、ということなのではないでしょうか。
つまり、経済のパイが拡大することで、人々への分配が拡大し、その分配にありつくのに有利だったのが、会社に入ることであり、都市に出ることであって、そのためには学歴を上げることが求められた。そして、それが一時期、階層上昇をともなっていたかのように見えた、ということなのではないでしょうか。
しかもそれ、つまり家計の向上は、工業社会つまり製造業中心の、単純労働を繰り返す分業システムが採用された、工場での労働によって手に入れることができる。このことが基本でした。
それは、極論すれば、働けさえすれば、つまり労働力さえ持っていれば、誰もが就労することができ、賃金を得ることができる仕組みでした。 それは、上層ブルーカラーや農業・自営業のような熟練を必要としない、いわば単能工の世界であり、ただindustrialつまり勤勉でありさえすれば、基本的に誰でもが働け、その意味において、誰もが本質的に同じだとされる社会だったのではないでしょうか。
コツコツと与えられた仕事を勤勉に続けること、このことがものをいったのです。そこでは、先に述べたように、すべての人が発達する存在だったのです。

そしてこのような社会のあり方は、競争と選抜のシステムに親和的な人間観と社会観を持ったものでもありました。その最たるものが、入試です。
入試は、すべての子どもたちに保障された、つまり学校に進学することで、すべての子どもたちに開かれた競争の機会です。誰でもが参加でき、合格するのは誰でもよいのです。
求められているのは、ある尺度による基準をクリアしていて、定員内に入っていること、それだけです。繰り返しますが、合格するのは、誰でもよいのです。だから、入試の基本は、ある時点での子どもたちの学習の到達度を測ることとなります。
一発勝負の、いわゆる機会の均等を基本としたテストでできるのは、テスト時点での完成度を測ること、つまり学んだことをどれくらい身につけて、どれくらいできるようになっているのかを測ることです。完成品を一つの基準で評価することと同じです。製造業の価値観と同じなのです。
だから、速さと高さという量が問題となります。ある時点で、どれくらいできるのかを測るのは、量の大きさ、つまり数字の大きさで表されますが、それを担保しているのは、それまでにどれくらい早く達成して、どれくらい高い水準でそれを身につけているのかという、量の大きさでしかないからです。しかもこの評価は、一つの尺度で数値を並べて、上からとっていく相対評価です。
ですから、誰もが人との比較の中で、より早く、より多く、より高く、という競争に駆り立てられることとなります。
価値観が単一で、画一的な人間観で構成されていて、その人間観にもとづく労働、つまり労働力の支出によって価値をつくりだし、それが利潤として社会に生み出される工業社会においては、このような単一の価値尺度にもとづく競争が経済発展を促します。
その結果、人々は働き口を求めて農村から都市へと移動して、都市の人口集中を推し進め、増える人口が安価な労働力として働き、豊かな購買力を形成することで、経済のパイを大きくし、それが人々への分配を増やします。これが、出世だと受け止められたのではないでしょうか。必ずしも社会階層を上昇したことで、家計が豊かになったということではないのです。
その意味ではみんなが出世したのですし、ほとんど誰も出世してはいなかったともいえるのではないでしょうか。ただ、学校を通して、均質で平等な人間観が広がり、その人間観にもとづいて制度がつくられ、分業体制、つまり単純労働の繰り返しによる生産労働に就くことができるようになった結果、製造業の拡大にともなって、社会の分配が増えただけだったということでもあるのです。
ですから、不況になって、社会的なパイが縮小して、分配が減っていくと、同じ階層にいても、人々の肌感覚からは不平等になった、または格差が広がったということになるのではないでしょうか。
でも、この肌感覚はバカにできません。格差が広がっているという感覚には、もう一つの側面があるように思えるからです。単に、社会の経済的なパイが小さくなって、分配が減っているということだけではない、何かがこの社会で起こっているのではないでしょうか。
社会が不況になった1990年以降も、階層移動のしやすさとしにくさ、つまり相対移動率に、大きな変化はない。このことは述べたとおりです。しかし、困窮者が増えているという感覚がある。それは多分、社会経済のパイが縮小して、分配が減っているからだということになります。しかし、ここで注意すべきことがあるのです。
再び、学校によって階層が再生産されるという議論が喧しくなっています。それは、学校によって貧困が再生産されるという議論としてとらえた方がよいのだろうとも思います。
すでに述べたように、いまは縮小する社会にあって、階層上昇しても賃金はそんなに増えることもありませんし、さらに転職市場の拡大で、中途採用が増え、人々の就労が流動化していきますが、転職で賃金は上昇するわけではありません。むしろ、非正規などの不安定な仕事を転々とするような就労形態が続く人々が多数生まれてしまっています。
そしてその裏で、次のようなことが起こってはいないでしょうか。つまり、工業社会が終焉を迎えて、大衆消費社会へと移行することで、それまで大量生産・大量消費のモデルにもとづいて、分業体制にもとづく単純労働の集積で構成されていた工場の労働が減少して、その結果、単純労働による大量の就業が困難となり、失業率が上がった。
ブルーカラー層や下層ホワイトカラー層の仕事が、営業や接客などの職種が求めるような、さらには介護や看護職などの求人が増えることで必要とされるような、高度なコミュニケーションスキルや対人関係形成力を必要とするものへと転化していった。つまり、誰でもが就労できる、単純労働の市場が縮小してしまった。こういうことはないでしょうか。
それらの仕事は一時、「感情労働」と呼ばれたりしました。それは、ルーティンな単純労働を求めるのではなく、相手の感情に寄り添いつつ、相手の感情によって自分の人格そのものが評価されてしまうかのような、難しい対人関係の中におかれざるを得ない仕事であり、誰でもが就けるわけではない、ストレスフルな労働なのです。しかもそれらが、下層化つまり不安定なアルバイトやバートなどの非正規労働として急速に広がっていて、所得の分配が減少して、社会的な下方平準化が起こってしまうのです。
こうした、労働の質の変化がもたらしたある種の不公平感も、格差が拡大したという肌感覚の正体の一部なのではないでしょうか。

それらを受けて、また学校による貧困の再生産がいわれ、貧困と学力とがかかわることが指摘され、学力と非認知能力がかかわっているといわれるようになっています。
学校による階層の再生産論は、もともとは、経済格差の再生産論であり、学校は選抜システムとして、家庭の経済力を選抜しているという議論でした。その後、それは子どもの遺伝的資質を選抜しているという議論や、子どもがおかれた家庭の文化的な環境を選抜しているという議論、さらにはそれらにもとづく生活習慣を選抜しているという議論など、さまざまな議論へと展開していきました。
さらにそれらは、家庭が持っている人間関係のあり方、とくに相互の承認関係をどのようにつくることができるのかという問題とかかわりがあるともいわれています。
しかし少し考えてみればわかるように、それらはすべて、がんばること、努力することを価値とする議論の変奏だといえます。つまり、努力しようと思えないこと、がんばろうと思えないことが問題なのだ、という議論です。
そして出てきたのが、やる気の格差論であり、やる気を持てるような人間関係にあるのかどうかという人間関係の格差論であり、それがもたらす非認知能力の低さという議論です。だから、非認知能力を高めれば、子どもたちはやる気が出て、がんばろうと思え、学力が上がる、こういう議論も散見されます。だから、褒めましょう、褒めて、自己肯定感を高め、やる気を出させましょう、というのが、この種の議論の論理です。
その是非は、また後ほど検討することとして、これらはすべて、工業社会の均質で画一的な人間観と社会観を引きずったままなのではないでしょうか。そして、そこから導かれるのは、ある尺度、たとえば学校の成績と家計の収入、つまりテストの点数という量と「おカネ」という量との結びつきから、その子どものがんばりや努力という人格的な面を評価しようとする議論なのではないでしょうか。その好意的なバージョンが、すでに述べた「みんなちがって、みんないい」なのではないでしょうか。
しかしそれが、子どもたちを追いつめてしまっているように思います。 いくら社会が変わり、価値観が変わり、人々の肌感覚が不平等の拡大へと動いていっても、いまだに、いえ、だからこそ、人々は学校という、過去に自分の家計の向上を実現してくれたと信じている制度を使って、よりよい収入を得ようとする行動をとり続けるのかも知れません。これこそが、学校の持つ慣性力の動力源なのです。学校は、工業社会の巨大な慣性力に動かされたままになっているのではないでしょうか。
\ 人生100年時代の社会のグランドデザインを描く/
\ 最新情報が届きます! /
牧野先生の記事を、もっと読む
連載:子どもの未来のコンパス
#1 Withコロナがもたらす新しい自由
#2 東日本大震災から学ぶwithコロナの中の自由
#3 Withコロナで迫り出すこの社会の基盤
#4 Withコロナがあぶりだす「みんな」の「気配」
#5 Withコロナが呼び戻す学校動揺の記憶
#6 Withコロナが再び示す「社会の未来」としての学校
#7 Withコロナが暴く学校の慣性力
#8 Withコロナが問う慣性力の構造
#9 Withコロナが暴く社会の底抜け
#10 Withコロナが気づかせる「平成」の不作為
#11 Withコロナが気づかせる生活の激変と氷河期の悪夢
#12 Withコロナが予感させる不穏な未来
#13 Withコロナで気づかされる「ことば」と人の関係
#14 Withコロナで改めて気づく「ことば」と「からだ」の大切さ
#15 Withコロナが問いかける対面授業って何?
#16 Withコロナが仕向ける新しい取り組み
#17 Withコロナが問いかける人をおもんぱかる力の大切さ
#18 Withコロナで垣間見える「お客様」扱いの正体
#19 Withコロナで考えさせられる「諦め」の怖さ
#20 Withコロナ下でのオリパラ開催が突きつけるもの
#21 Withコロナで露呈した「自己」の重みの耐えがたさ
#22 Withコロナであからさまとなった学校の失敗
#23 Withコロナの下で見えてきたかすかな光・1
#24 Withコロナの下で見えてきたかすかな光・1.5
#25 Withコロナの下で見えてきたかすかな光・2
連載:学びを通してだれもが主役になる社会へ④
#1 あらゆる人が社会をつくる担い手となり得る
#2 子どもたちは“将来のおとな”から“現在の主役”に変わっていく
#3 子どもの教育をめぐる動き
#4 子どもたちに行政的な措置をとるほど、社会の底に空いてしまう“穴”
#5 子どもたちを見失わないために、社会が「せねばならない」二つのこと
#6 「学び」を通して主役になる
新着コンテンツ