
【張り子作家・アート大福さん】絵本のように可愛く不思議な世界。まったくの未経験から独学で作家活動をスタート。「私にもできる!」と思ってほしい
2024.02.20
仕事・働き方
2020.10.9
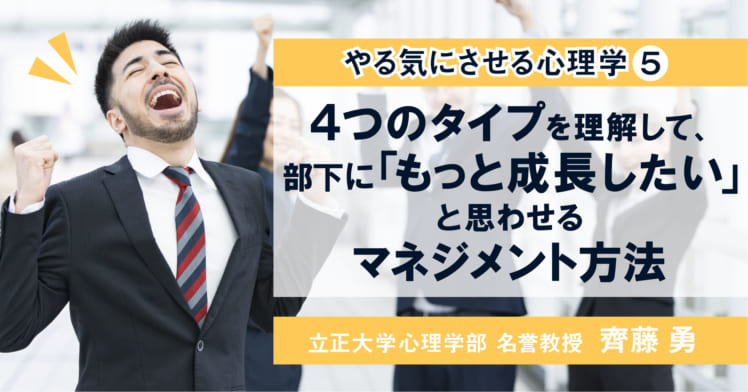
立正大学心理学部名誉教授
齊藤 勇

対人心理学者、文学博士1943年生まれ。早稲田大学大学院文学研究科博士課程修了。現在、立正大学名誉教授、日本ビジネス心理学会会長。 対人・社会心理学、特に人間関係の心理学、中でも対人感情の心理、自己呈示の心理などを研究 。TV番組「それいけ!ココロジー」に出演し監修者を務めるなど、心理学ブームの火つけ役となった。『人間関係の心理学』『やる気になる・させる心理学』など、編・著書・監修多数。
私が若いときから、友人たちがお酒の席に集まると「最近の若い連中はやる気がない、困ったものだ」と嘆くのをよく耳にしていました。今の若い子みんなというわけではないですが、「ゆとり世代」「さとり世代」と言われる新人と一緒に仕事をする社員、はっぱをかけてもやる気になってくれない部下に、どうやったらやる気にさせられるか悩んでいる上司は少なくないと思います。
やる気のない社員ばかりではありませんよね? やる気もあるし、それなりに成果も出してくれている社員もたくさんいますが、「チームのために貢献してくれたらもっといいのに」「もっと上昇志向をもってマネジメント職をねらってくれたらいいのに」といったようにもっと自分の成長へのモチベーションをもってほしい、もう一段高いスキルを身につけてもらいたいと思う部下をお持ちの上司もたくさんいらっしゃると思います。
そもそも、人間にはもともとやる気はあるのですから、やる気がないというよりも、仕事の目標がはっきりしていなくて何をやっていいかわからない、今やっている仕事の成果について魅力がないということでやる気が失せている場合もあります。
このあたりについてはまた後日、詳しくお話しさせていただこうかと思いますが、今回は、その人が持っている特性に対して適切に働きかけてあげることで、行動を喚起させたり、もう一段高いスキルを目指して行動してくれるためにはどうしたらよいか?をお話させていただきたいと思います。
人はそれぞれ違った個性を持っていますし、仕事に対してどんなところに魅力を感じているかはみな違います。まずはそこをしっかりと認識をして、上司は部下一人ひとりの個性や特性に合った働きかけをすることが大切です。そこを間違えるとなかなかやる気もあがらず、人によっては「自分にはこの仕事が合わない」といってやる気が失せてしまう人もいます。
アメリカ の心理学者デイビッド・C・マクレランドは、仕事をする人の行動の動機を「達成動機(欲求)」「親和動機(欲求)」「権力動機(欲求)」「回避動機(欲求)」の4つに分類し、この理論を社員のモチベーションマネジメントに活用している企業も少なくありません。
タイプ①:成長できることにやりがいを見出すタイプ(達成動機型)
タイプ②:できることしかやらないタイプ(失敗回避型)

前回(「やる気にさせる心理学④」では、個性によって行動のさせかたが変わるというお話をしました。前回は「成功に対する報酬を得ることよりも、自分で成功させたい、前回よりももっと良い結果をだしたい(達成欲求が強い)」という人、「失敗を恐れて、絶対できると思うことしかやらないか、成功する確率がとても低いことをやろうとする(失敗回避欲求が強い)」人についてお話しました。こういったタイプの人には、前回の記事で説明しています。
▶ やる気にさせる心理学④ 「個性によってやる気の出させ方は変わる」
タイプ➂:地位や権力、影響力が欲しいタイプ(権力動機型)

自分が中心になって動いて人に影響を与えられる仕事ならやる気になるという人もいます。これを心理学では「権力欲求の強い人」と言います。自分がどれだけ努力したかで成果が出ることを好む達成欲求の高い人とはまた少し違い、「『長』が付くものに憧れる」、「人に使われるより使うほうになりたい」という気持ちが強いタイプはこの傾向が強い人ですね。「ライバル」がいると俄然燃えるタイプもそうです。内的な動機から行動する「達成欲求」とは違って、「地位」「名誉」といった報酬が、その人を行動させます。
また、このタイプは自分が注目される、されないということよりも、自分がいかに人に影響力を与えられるかということに魅力を感じるので、他人がどう思おうと気にしないところがあります。権力を持ちたいことは、「上昇志向の表れ」といえば聞こえが良いですが、それだけでは自分の本来の欲求を満たすことができないことを伝えることが大切です。
タイプ④:みんなと一緒がいい、一人では頑張れないタイプ(親和動機型)

「人のために頑張りたい」、「人に感謝されることをしたい」、「一人でいることは嫌」という気持ちが強い人もいます。こういったタイプの人を心理学では、「親和欲求の強い人」と言います。
このタイプの人は、チームの達成に魅力を感じてくれるので、部内が居心地よく、ほかの社員に対してもいい影響を与えてくれますが、このタイプも自己を成長させたいという欲求よりも、人のために動くという外的刺激と、チームで達成するという報酬を得られることがやる気となり行動を起こします。親和欲求は社会においてはとても大切な欲求なので、その特性を組織だけでなく、自分の成長にも関連づけてあげると良いでしょう。
権力欲求の強い部下に自己の成長を意識させるためには、その欲求を間違った形で生かさないようにしっかりと理解させることが大切です。一般的にリーダーシップと呼ばれる力は、対人心理学の中では「社会的影響力」といい、以下の5つに分類されます。
「強制勢力」と「報酬勢力」傾向のある上司は、権力をもっていても長続きしません。「正当勢力」と「専門勢力」傾向にある上司は、部下が自分を好きか嫌いかによって変わるので、これもどちらかというと長続きしません。
とても難しいことですが、人の上に立つ人になりたければ、「準拠勢力をもつ人」、つまり、相手に自分を好きになってもらう、信頼される、尊敬されることがリーダーの素質の1つであると理解してもらうことが大切です。
リーダーシップを発揮する相手との信頼関係を築くスキルを身につけることが本当の意味での欲求を満たすことにつながる、ということを理解させましょう。
「権力をもつ」ということは、その権力を行使する相手があってこそ、その欲求は満たされるというもの。権力をふるう相手との関係が築けていなければ、いくらスキルがあっても権力の振るいどころがなくなりますからね。

親和欲求が強すぎる部下は、チーム全体がうまく回ってくれればそれでいい、リーダーという立場にそんなに魅力を感じない人も少なくないのではないでしょうか。しかし、こういうタイプだからこそできるリーダーシップがあります。
これまで、カリスマ性や絶大な存在感、影響力を与えるリーダー像が主流でしたが、近年はメンバーが仕事に対して自律的に取り組み、メンバー同心でも密接な連携や協力を行うことが求められているという社会的要請から、新しいリーダーシップ論として、メンバーを下から支え奉仕する「サーバント・リーダーシップ」というリーダーシップの在り方も注目されています。

サーバント・リーダーシップは、メンバーからの信頼獲得につながり、メンバーの自律的なモチベーションを醸成するだけでなく、職場内の協力する風土を醸成させます。
このタイプの人は、サーバント・リーダーとしての素質を十分持っていますので、その特性を生かして、自分の成長意欲に目をむけてもらうよう働きかけてあげましょう。このタイプは、上司との信頼関係がしっかりとれていれば、多少厳しく言っても、組織のため、チームのために「自分が変わることを求められている」と感じてくれ、自己成長に意欲的になってくれます。
逆に、親和欲求の強い部下をもつ上司は、その居心地よさに甘んじないよう注意をしてください。
第一次安倍内閣では、現在の安倍総理を支持した議員を入閣させたとして「お友達内閣」と揶揄されたことがありましたね。その結果、多くの大臣が不祥事等を起こして辞任が相次ぎ、第一次安倍内閣はわずか1年で退陣となりました。
親和欲求の強い部下の言葉は、上司にとってはとても心地よいものかもしれません。ただ、上司のみなさんは、部下の成長のためにも、部下に対してお友達や家族のような「過剰な慣れ合い」で接しないよう適切な距離感を心がけてあげましょう。
人間は自分の欲求に合わないことをするとモチベーションが下がる傾向にあります。モチベーションはどんな組織においても非常に重要です。どんな人もモチベーションが低くなると、「誰かがやってくれる」という心理が働くのです。
心理学の実験にドイツのリンゲルマンが行った、「綱引きの実験」というのがありまして、昔、綱引きがオリンピックの種目になるほどメジャーだったことはご存知ですか?
綱引きをしたときに、一人ひとりの力を足すとどのくらい引けるかと計算すると、本来であればこれくらい綱を引けると算出されるのですが、実際はその計算通りではないのです。ほかの人がいるとモチベーションが低下してしまう心理現象が起こるためです。これを心理学ではリンゲルマン効果(社会的手抜き)といいます。
集団になったときにおこる心理的現象ではありますが、誰かがやってくれるだろうという心理が働くことで社員のモチベーションが下がってしまえば、組織としても十分な力を発揮できなくなってしまいますからね。
上司は部下がどのようなタイプなのかを理解し、適切な対応ができれば、単に社員にやる気を出させるためだけでなく、「自分をもっと成長させたい」という意欲を持たせることもでき、結果的に会社の生産性向上にもつながります。
\ 最新情報が届きます! /
あわせてよみたい
齊藤勇先生の「やる気にさせる心理学」
▶行動することでやる気は出てくる
▶やる気への行動プロセス
▶「本番に弱い人」にはこんなアプローチが効果的!
▶個性によってやる気の出させ方が変わる(達成欲求と失敗回避欲求)
▶4つのタイプを理解して、部下に「もっと成長したい」と思わせるマネジメント方法
▶やる気の違いは目標設定の違いにある! 「目標」が持てない部下に、自律的な行動を促すマネジメント
▶目標達成できない二つの要因を知って、部下のやる気をマネジメント!
▶自己効力感を高めるための4つのアプローチ方法
▶仕事が面白いと感じさせるフロー体験
▶テレワークの時代だからこそ、部下のやる気を育てる上司の7つの心得
▶「できないこと」を書き出すことが目標達成の近道
▶どうにもネガティブに考える自分を変える方法
▶やる気を継続している人が持っている、ある3つの感情とは?
▶人間関係の中の自分はどんなタイプ?自己分析してみよう
【相談】齊藤勇先生の「人間関係の心理学」
【第1回】職場でイジられキャラから脱出できなくてやる気失せるんです
【第2回】問題は夫や息子ではなくアナタ!(ご主人編)
【第3回】問題は夫や息子ではなくアナタ!(息子編)
【第4回】恋愛と仕事どっちが大事?アラサー女子が悩む大問題
【第5回】相談されやすい人がもつスキルとは?
【第6回】職場の人間関係がリセットされたらなんだかうまくいかない
【第7回】仕事のお願いが断れない私
【第8回】人にイライラしてしまう私
【第9回】ネガティブな彼女への正しい接し方は?
【第10回】自己中心的な同僚の対応に悩む私
【第11回】苦手な先輩との仕事のやり方で悩む私
【第12回】キャリアアップすべき?部署でまとめ役を求められるワーママ
【第13回】中高生の子どもと向き合うための親の持つべき心得
【第14回】やる気がありすぎる!とにかく一番が大好きな娘
【第15回】怖がりの息子が将来独立できるか心配
【第16回】これってモラハラ発言!?夫よ、私は言葉の暴力に傷ついている
【第17回】人に頼ってばかりの私
【第18回】高齢になった父との関係をよりよくするには
新着コンテンツ
この記事を担当した人
わん子

やる気ラボに古くからいる微魔女犬。やる気が失せると顔にでるためわかりやすい。my癒しは、滝と戦闘機と空を見上げること。